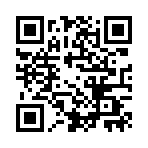2011年09月08日
奪われた “主役の座”???
その場所の “主” だったのに、いつの間にかその座を奪われていた・・・。
人間社会ではよくあることである。
さて、昨日某紙に 「水族館にブタ 『なぜいるのか』 と驚く客も」 というタイトルの
記事があったが、その内容は
・・・・・・・・ 熊本県上天草市の海中水族館 「シードーナツ」 でミニブタ2頭が人気
になっている。来館者に動物愛護意識を高めてもらおうと、軽い気持ちで
飼育・展示したところ 「水族館にブタ」 という異色の組み合わせが思わ
ぬ反響を呼んだ。
お座りなどの芸も身に付け、すっかり魚たちから主役の座を奪っている。
2頭はオスの 「シード君」 とメスの 「ナッちゃん」。 親は別だが偶然
共に2月14生まれ。
飼育・展示を始めたのは3月で、簡単にペットを捨てる風潮に警鐘を鳴ら
す目的。「体温を感じられる動物に触れてもらうことが命の大切さに理解
を深める機会になる」 と考えたという。ミニブタを選んだのは愛嬌があり
親しみやすいからだ。
「なぜ、ブタがいるのか」 と驚く客も多く、そのたびにスタッフが経緯を
説明している。
特に子どもたちに人気があり、 「耳が温かい」 「かわいくて癒される」
などと身体をなでたり、携帯電話のカメラで写真を撮ったり、魚よりも2頭
目当てに訪れる客もいるという。
同水族館でもやむを得ない事情で飼えなくなったペットの魚を引きとって
いる。施設管理担当のMさん (34才) は、「楽しくミニブタと触れあって
命を肌で感じ、動物を大切にする気持ちを持ってほしい」 という。
ミニブタは3年ほどで50~80キロの体重になるが、「いつまでも水族館
のマスコット的な存在であり続けてほしい」 とも語った・・・・・・・
というものである。
「水族館に (本来いるはずのない?) ブタがいる」 というのはたしかに突飛で面
白い発想であるし、また見ることが中心で直接触れ合うことは基本的にあまりなく、
イルカやアシカのショーなど一部を除いて “芸” などを見せてくれることもない水中
動物よりも、ミニブタのような動物の方がより親しみやすいことも否定できないだろう。
公営、民間を問わず施設側としても従来の定型的な手法だけで来館者数を維持・増
加させることが困難といわれる昨今、今後もこういう 「あれっ」 と思わせる意外性
に富んだ企画はますます必要になるかもしれない。
しかしそれはそうと、この水族館がミニブタを飼育・展示するにあたっての 「簡単に
ペットを捨てる風潮に警鐘を鳴らす」 という大上段的な目的や理由についてはその
効果などについて若干なりとも疑問視せざるを得ない。「楽しく触れ合って命を肌で
感じる」 という部分については基本的に否定できないが、それはどちらかといえば
「ペットを飼い始める動機」 に関することであり、 「一旦飼い始めたペットを放棄し
ない」 ということには必ずしも直結しないからである。
ペットを飼い始める時にはほとんどの人にとって 「生き物の生命の鼓動を直接肌で
感じられる」 「かわいい」 「癒される」 という理由が大半を占めるだろう。だが問
題は 「その気持ちを (ペットにとっての) 最期の時まで維持できるか」 というこ
とだ。当初の 「かわいい」 という気持ちが薄れてくることに加え、面倒や世話が
思いのほか大変であることから、次第に 「もう飽きた」 とか 「後は知らない」 と
いうような身勝手極まりない方向に進んでいくのである。
前述のように、この水族館のユニークな取り組み自体は大いに興味をそそられると
ころであるし、来場者数の低下に悩む全国のテーマパークとして見習う点は少なく
ないだろう。しかし発する 「社会的メッセージ」 についてはあまり大きくしない方
がむしろより多くの共感を呼ぶことになるというものではないか。
飼い主宅の “主役” はあくまでも
自分である、という自覚を持っている
!? こじろう
人間社会ではよくあることである。
さて、昨日某紙に 「水族館にブタ 『なぜいるのか』 と驚く客も」 というタイトルの
記事があったが、その内容は
・・・・・・・・ 熊本県上天草市の海中水族館 「シードーナツ」 でミニブタ2頭が人気
になっている。来館者に動物愛護意識を高めてもらおうと、軽い気持ちで
飼育・展示したところ 「水族館にブタ」 という異色の組み合わせが思わ
ぬ反響を呼んだ。
お座りなどの芸も身に付け、すっかり魚たちから主役の座を奪っている。
2頭はオスの 「シード君」 とメスの 「ナッちゃん」。 親は別だが偶然
共に2月14生まれ。
飼育・展示を始めたのは3月で、簡単にペットを捨てる風潮に警鐘を鳴ら
す目的。「体温を感じられる動物に触れてもらうことが命の大切さに理解
を深める機会になる」 と考えたという。ミニブタを選んだのは愛嬌があり
親しみやすいからだ。
「なぜ、ブタがいるのか」 と驚く客も多く、そのたびにスタッフが経緯を
説明している。
特に子どもたちに人気があり、 「耳が温かい」 「かわいくて癒される」
などと身体をなでたり、携帯電話のカメラで写真を撮ったり、魚よりも2頭
目当てに訪れる客もいるという。
同水族館でもやむを得ない事情で飼えなくなったペットの魚を引きとって
いる。施設管理担当のMさん (34才) は、「楽しくミニブタと触れあって
命を肌で感じ、動物を大切にする気持ちを持ってほしい」 という。
ミニブタは3年ほどで50~80キロの体重になるが、「いつまでも水族館
のマスコット的な存在であり続けてほしい」 とも語った・・・・・・・
というものである。
「水族館に (本来いるはずのない?) ブタがいる」 というのはたしかに突飛で面
白い発想であるし、また見ることが中心で直接触れ合うことは基本的にあまりなく、
イルカやアシカのショーなど一部を除いて “芸” などを見せてくれることもない水中
動物よりも、ミニブタのような動物の方がより親しみやすいことも否定できないだろう。
公営、民間を問わず施設側としても従来の定型的な手法だけで来館者数を維持・増
加させることが困難といわれる昨今、今後もこういう 「あれっ」 と思わせる意外性
に富んだ企画はますます必要になるかもしれない。
しかしそれはそうと、この水族館がミニブタを飼育・展示するにあたっての 「簡単に
ペットを捨てる風潮に警鐘を鳴らす」 という大上段的な目的や理由についてはその
効果などについて若干なりとも疑問視せざるを得ない。「楽しく触れ合って命を肌で
感じる」 という部分については基本的に否定できないが、それはどちらかといえば
「ペットを飼い始める動機」 に関することであり、 「一旦飼い始めたペットを放棄し
ない」 ということには必ずしも直結しないからである。
ペットを飼い始める時にはほとんどの人にとって 「生き物の生命の鼓動を直接肌で
感じられる」 「かわいい」 「癒される」 という理由が大半を占めるだろう。だが問
題は 「その気持ちを (ペットにとっての) 最期の時まで維持できるか」 というこ
とだ。当初の 「かわいい」 という気持ちが薄れてくることに加え、面倒や世話が
思いのほか大変であることから、次第に 「もう飽きた」 とか 「後は知らない」 と
いうような身勝手極まりない方向に進んでいくのである。
前述のように、この水族館のユニークな取り組み自体は大いに興味をそそられると
ころであるし、来場者数の低下に悩む全国のテーマパークとして見習う点は少なく
ないだろう。しかし発する 「社会的メッセージ」 についてはあまり大きくしない方
がむしろより多くの共感を呼ぶことになるというものではないか。
飼い主宅の “主役” はあくまでも
自分である、という自覚を持っている
!? こじろう