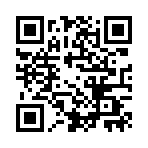2010年07月31日
『利便性=好都合』 とはかぎらない???(その1)
昨日、ある業者から自宅の固定電話に連絡があり、家内がそれを受けた際のこと。
「何度か電話させていただいたんですが、いらっしゃらなかったようで連絡が遅くな
りました。『着信』 が残っていませんでしたか」 というようなことをその女性担当
者が口にしたという。
「私はしっかりと仕事 (電話連絡) をしたんです」 ということを強調したい気持も
よくわかる。しかし少なくとも今回、当方には電話を受ける義務のある用件ではな
かったことからして、いくらなんでも 「『着信』 が残っていませんでしたか」 という
のは余計で、しかも顧客側に発する一言としてふさわしいとはいえないだろう。
まあそれはともかくとして、この 「着信記録」 というもの、携帯電話が普及してか
らは “あたりまえ” という意識になっているが、今から十数年ほど前くらいの固定
電話では、まだ一般的な機能とはいえなかったおぼえがある。
今や一人に一台 (以上) の携帯電話所持の時代とはいえ、ことに業務関係の用
件などはまだ事業所や家庭の固定電話にかかってくることも少なくないわけで、そ
のようなとき 「着信記録」 という機能は大変利便性が高いことはいうまでもない
し、また非通知電話などとの区別も容易にできてイタズラ電話防止にも大きく貢献
していることも疑いない。しかし反面、すべてにおいてその 「利便性=好都合」 と
はかぎらないのもまた事実である。
たしかに辞書で 「利便」 ということばの意味を調べると、「都合のよいこと」 あ
るいはそれに類することが書かれているが、日常生活の 「生きた」 さまざまな
場面ではその意味通りにならないことも少なくない。つまり今回のことでいえば、
「着信記録など残らなかった頃の方が、かえって都合がよかった」 ということも
それなりに存在するのである。その具体的なことなどについては 「こじろう117」
・・・『利便性=好都合』 とはかぎらない???(その2)・・・ で触れてみることに
したいと思う。
犬用の便利グッズの中に、自分にとって
都合のよくないものがいくつかあること
とに気づいている!? こじろう
「何度か電話させていただいたんですが、いらっしゃらなかったようで連絡が遅くな
りました。『着信』 が残っていませんでしたか」 というようなことをその女性担当
者が口にしたという。
「私はしっかりと仕事 (電話連絡) をしたんです」 ということを強調したい気持も
よくわかる。しかし少なくとも今回、当方には電話を受ける義務のある用件ではな
かったことからして、いくらなんでも 「『着信』 が残っていませんでしたか」 という
のは余計で、しかも顧客側に発する一言としてふさわしいとはいえないだろう。
まあそれはともかくとして、この 「着信記録」 というもの、携帯電話が普及してか
らは “あたりまえ” という意識になっているが、今から十数年ほど前くらいの固定
電話では、まだ一般的な機能とはいえなかったおぼえがある。
今や一人に一台 (以上) の携帯電話所持の時代とはいえ、ことに業務関係の用
件などはまだ事業所や家庭の固定電話にかかってくることも少なくないわけで、そ
のようなとき 「着信記録」 という機能は大変利便性が高いことはいうまでもない
し、また非通知電話などとの区別も容易にできてイタズラ電話防止にも大きく貢献
していることも疑いない。しかし反面、すべてにおいてその 「利便性=好都合」 と
はかぎらないのもまた事実である。
たしかに辞書で 「利便」 ということばの意味を調べると、「都合のよいこと」 あ
るいはそれに類することが書かれているが、日常生活の 「生きた」 さまざまな
場面ではその意味通りにならないことも少なくない。つまり今回のことでいえば、
「着信記録など残らなかった頃の方が、かえって都合がよかった」 ということも
それなりに存在するのである。その具体的なことなどについては 「こじろう117」
・・・『利便性=好都合』 とはかぎらない???(その2)・・・ で触れてみることに
したいと思う。
犬用の便利グッズの中に、自分にとって
都合のよくないものがいくつかあること
とに気づいている!? こじろう
2010年07月30日
『分析』 といえるほどのことか???(その2)
「こじろう117」・・・『分析』 といえるほどのことか???(その1)・・・の続きである。
昨日は 「今年上半期のヒット商品」 に関して、某有名シンクタンク研究員がコメント
した 「価格を抑えつつ、品質の高い商品が今後も人気を呼ぶ」 という “分析” に
ついて、専門家の “分析” といえるほどのものではない、つまり 「誰でもわかるこ
とを、ただもっともらしく言っているにすぎないのでは」 ということを述べた。
新聞に限らず、メディアで斯界の専門家の (分析) コメントが出てくることはよくあ
るが、「さすがにその道の専門家らしい 『なるほど、と納得させられる』 見解」 と
思わされるものがある反面、「専門家の分析といえるほどのものか」 との疑問を抱
かざるをえないものも少なくない。
誰でもわかるような 「あたりまえのこと」 「毒にも薬にもならないこと」 をもっともらし
くTVのニュース番組などでコメントする名人?第一人者?として有名な、警視庁元
捜査一課長T氏のことについては以前 「こじろう117」・・・『毒にも薬にも』・・・が一番
???で取り上げたことがある。その “T氏クラス” にもなると、今や伝説?となって
いる某ニュース番組内のやりとりで、
キャスター・・・「Tさん、今回の事件の犯人像、どのように分析されますか」
T氏 ・・・「うーん、犯人は男性、もしくは女性の可能性もありますね」
キャスター・・・「はあ」
T氏 ・・・「さらにいえば、犯人の年齢はこの手口から推測して、20代から30代、
あるいは40代から50代、場合によっては60代以上ということも考え
られるでしょう」
キャスター・・・「・・・・・」
というようなものがあったと聞くが、このくらいになるともはや 「殿堂入り」 レベルであ
り、視聴者もその 「名人芸?」 を最初から期待しているフシすらある。
メディアに限らず日常の生活の中でも、やはり誰でもあたりまえに考えつくことを、いか
にも 「物知り顔」 でもっともらしく話す人は結構多いように思われる。もっともそれは必
ずしも批判の対象となるわけではなく、ある意味 「話術に長けている」 という見方もで
きるかもしれない。しかし、そういうことが度を過ぎるほどになると周囲も徐々に見抜き始
め、その人のことを 「軽い人間だ」 とか 「大して中身のない人だ」 と思うようになる
のは避けられないだろう。
飼い主が 「うちの “こじろう” は・・・」
と、いかにもわかったような口ぶりで
話すことに納得がいかない!?
こじろう
昨日は 「今年上半期のヒット商品」 に関して、某有名シンクタンク研究員がコメント
した 「価格を抑えつつ、品質の高い商品が今後も人気を呼ぶ」 という “分析” に
ついて、専門家の “分析” といえるほどのものではない、つまり 「誰でもわかるこ
とを、ただもっともらしく言っているにすぎないのでは」 ということを述べた。
新聞に限らず、メディアで斯界の専門家の (分析) コメントが出てくることはよくあ
るが、「さすがにその道の専門家らしい 『なるほど、と納得させられる』 見解」 と
思わされるものがある反面、「専門家の分析といえるほどのものか」 との疑問を抱
かざるをえないものも少なくない。
誰でもわかるような 「あたりまえのこと」 「毒にも薬にもならないこと」 をもっともらし
くTVのニュース番組などでコメントする名人?第一人者?として有名な、警視庁元
捜査一課長T氏のことについては以前 「こじろう117」・・・『毒にも薬にも』・・・が一番
???で取り上げたことがある。その “T氏クラス” にもなると、今や伝説?となって
いる某ニュース番組内のやりとりで、
キャスター・・・「Tさん、今回の事件の犯人像、どのように分析されますか」
T氏 ・・・「うーん、犯人は男性、もしくは女性の可能性もありますね」
キャスター・・・「はあ」
T氏 ・・・「さらにいえば、犯人の年齢はこの手口から推測して、20代から30代、
あるいは40代から50代、場合によっては60代以上ということも考え
られるでしょう」
キャスター・・・「・・・・・」
というようなものがあったと聞くが、このくらいになるともはや 「殿堂入り」 レベルであ
り、視聴者もその 「名人芸?」 を最初から期待しているフシすらある。
メディアに限らず日常の生活の中でも、やはり誰でもあたりまえに考えつくことを、いか
にも 「物知り顔」 でもっともらしく話す人は結構多いように思われる。もっともそれは必
ずしも批判の対象となるわけではなく、ある意味 「話術に長けている」 という見方もで
きるかもしれない。しかし、そういうことが度を過ぎるほどになると周囲も徐々に見抜き始
め、その人のことを 「軽い人間だ」 とか 「大して中身のない人だ」 と思うようになる
のは避けられないだろう。
飼い主が 「うちの “こじろう” は・・・」
と、いかにもわかったような口ぶりで
話すことに納得がいかない!?
こじろう
2010年07月29日
『分析』 といえるほどのことか???(その1)
先日の某紙朝刊に、この時期恒例の 「上半期ヒット商品」 に関する特集記事を
見つけた。その (一部) 内容は、
・・・・・長引く不況などにより閉塞感が漂った今年の上半期、手頃な価格でリッチ
感のある 「プチぜいたく商品」 などに消費者の人気が集まった。
食品としてはM社の 「テキサスバーガー (400円~420円) 」 な
どのビッグアメリカンシリーズ、R社が火付け役になったコンビニ各社の
「150円ロールケーキ」 など、価格は少し高めだが、ボリュームや高級
感のある商品が人気を呼んだ・・・・・
と続き、「まあ、そんなところだろう」 とのんきに読み進めていたが、途中、有名な
シンクタンク研究員の (今年上半期の商品傾向等に関する) “分析” コメントが
登場したところで、「オヤッ」 と思わされることになってしまった。
その “分析” コメントとは、「価格を抑えつつ、品質の高い商品が今後も人気を
呼ぶのでは・・・」 というものである。
たしかにこの “分析”、「非の打ちどころのない、もっともなもの」 といえばその
通りである。しかし、まず 「価格を抑えつつ」 という部分。人気を呼ぶ商品とは
昔も今も普通に考えて 「価格が抑えられた」 ものであるのはあたりまえで、とり
たてて今年に限ったこととはいえないだろう。また、「品質の高い商品」 というこ
とに関しても、それをいうなら逆に 「質の悪い商品」 はやはり昔も今も人気を呼
ぶはずはないわけで、これも特に強調されるほどのことではないことである。
つまり、「 “価格を抑えつつ” “品質の高い商品” が人気を呼ぶ」 などという
こと (分析) は 「“有名シンクタンクの研究員” でなくても、いわば誰でも普
通にわかる (いえる) ことではないか」 すなわち 「専門家の “分析” 以前
のことではないか」 ということである。
新聞以外でも、TVのニュース・ワイドショー番組や雑誌の記事の中で目にしたり、
耳にしたりする専門家と称する人たちの 「?と思われるコメント」 、およびメディ
アに限らず、我々の日常生活の中で、「物知り顔でもっともらしいことをいう人たち」
のことについては 「こじろう117」・・・『分析』 といえるほどのことか???
(その2) で触れたいと思う。
既にわかっていることなのに、飼い主
に「もっともらしくいわれる」 のを
迷惑に感じている!? こじろう
見つけた。その (一部) 内容は、
・・・・・長引く不況などにより閉塞感が漂った今年の上半期、手頃な価格でリッチ
感のある 「プチぜいたく商品」 などに消費者の人気が集まった。
食品としてはM社の 「テキサスバーガー (400円~420円) 」 な
どのビッグアメリカンシリーズ、R社が火付け役になったコンビニ各社の
「150円ロールケーキ」 など、価格は少し高めだが、ボリュームや高級
感のある商品が人気を呼んだ・・・・・
と続き、「まあ、そんなところだろう」 とのんきに読み進めていたが、途中、有名な
シンクタンク研究員の (今年上半期の商品傾向等に関する) “分析” コメントが
登場したところで、「オヤッ」 と思わされることになってしまった。
その “分析” コメントとは、「価格を抑えつつ、品質の高い商品が今後も人気を
呼ぶのでは・・・」 というものである。
たしかにこの “分析”、「非の打ちどころのない、もっともなもの」 といえばその
通りである。しかし、まず 「価格を抑えつつ」 という部分。人気を呼ぶ商品とは
昔も今も普通に考えて 「価格が抑えられた」 ものであるのはあたりまえで、とり
たてて今年に限ったこととはいえないだろう。また、「品質の高い商品」 というこ
とに関しても、それをいうなら逆に 「質の悪い商品」 はやはり昔も今も人気を呼
ぶはずはないわけで、これも特に強調されるほどのことではないことである。
つまり、「 “価格を抑えつつ” “品質の高い商品” が人気を呼ぶ」 などという
こと (分析) は 「“有名シンクタンクの研究員” でなくても、いわば誰でも普
通にわかる (いえる) ことではないか」 すなわち 「専門家の “分析” 以前
のことではないか」 ということである。
新聞以外でも、TVのニュース・ワイドショー番組や雑誌の記事の中で目にしたり、
耳にしたりする専門家と称する人たちの 「?と思われるコメント」 、およびメディ
アに限らず、我々の日常生活の中で、「物知り顔でもっともらしいことをいう人たち」
のことについては 「こじろう117」・・・『分析』 といえるほどのことか???
(その2) で触れたいと思う。
既にわかっていることなのに、飼い主
に「もっともらしくいわれる」 のを
迷惑に感じている!? こじろう
2010年07月28日
『予防が大切』 と言われても!!!(その2)
「こじろう117」・・・『予防が大切』 と言われても!!!(その1)・・・で、「熱中症」
のことを取り上げたばかりの27日、某紙朝刊の第一面に 「熱中症 9400人 搬送
57人 死亡・・・全国一週間まとめ・・・“過去最高に”」 というタイトルの大きな記事が
出ていた。
それによると、7月・8月を通じた熱中症による死者数は、2008年が47人、2009年
が16人であったのに対し、今年はなんと、たったの一週間でそれらをはるかに上回る
という、過去に例を見ない 「とんでもない事態」 になっているという。
さて、昨日は 「“熱中症” 予防」 の難しさについて、特に中高年層に関しては、まず
「観念や意識の問題があるのでは」 ということを述べたが、今日はさらに具体的な予防
の難しさについてである。
昨日紹介した某紙記事の 4. 「 (熱中症にかからないために) 日常生活で気をつ
けること」 によれば、
1. のどが渇いていなくても、水分をこまめに補給すること。お年寄りは脱水が進んで
ものどの渇きを覚えにくいので、特に注意が必要。
2. 汗をかいて水を飲むと血中濃度が薄くなる。体内の電解質バランスが崩れ熱中症
が進む原因となる。梅干しや塩分入りキャンディー等も必要に応じてとるようにした
い。
3. 30度以上になると発症しやすくなるので、部屋の温度を知るために寒暖計があっ
たほうがよい。エアコンや扇風機も必要以上に嫌わず上手に使うべきだ。
と紹介されている。
まず、1. についてであるが、水 (分) というのは普通、のどが渇いているからこそ
摂取したい (飲みたい) と思うわけであり、そうでないときに 「こまめに水分補給」
するにはそれなりの意識が必要である。また、いわゆる 「ビール党」 の人たちは、夏
場は夜になって飲むビール (特に1杯目) をより美味しくするために、日中の水分摂
取を極力控えようとする (かつての自分もそうだった) が、中高年になったら、そうい
う “ムチャ” は考えものということか。
次に、2. について。「体内の電解質バランス」 と言われても、素人にはなかなか難
しく、ピンとこない話である。個人的には “梅干し” ほど苦手なものはないし、また猛
暑のなか、キャンディーを口に含むのにもそれなりの覚悟?を要する人は (自分も含
めて) 少なくないのではなかろうか。
3. について。 「エアコンは嫌い」 というほどではないとしても、特に中高年の場合
は 「“効果的な活用” ができているか」 ということに大いに疑問の余地がある。その
機能を上手に使いこなせないと、逆に身体を部分的に冷やし過ぎてしまったりして別の
意味で体調を崩したり、具合が悪くなってしまうこともありうる。またこれだけ気温が高
いと、扇風機など回しても 「“熱風” が襲ってくるだけでかえって暑くなる」 などと考
えてしまうフシもある。
以上、「予防が大切」 と具体的に気をつけることを聞かされて、頭では理解できたとし
ても、実際に行動に移すのはなかなかやっかいで難しい面がある。最も大切なことは、
やはりこの連日の猛暑を 「侮らない」 ということである。ことに中高年は、「自分の若い
時分はエアコンなどなくても、また水分など大して補給しなくてもこの程度の暑さは簡単
に乗り切ったものだ」 という妙な自慢や過信を捨てて、「謙虚な気持ち?で猛暑と向き
合う」 ことが肝要であると思われる。
自分が熱中症になりかけたとき、
「果たして飼い主がちゃんと気づ
いてくれるのか」 と心配でなら
ない!? こじろう
のことを取り上げたばかりの27日、某紙朝刊の第一面に 「熱中症 9400人 搬送
57人 死亡・・・全国一週間まとめ・・・“過去最高に”」 というタイトルの大きな記事が
出ていた。
それによると、7月・8月を通じた熱中症による死者数は、2008年が47人、2009年
が16人であったのに対し、今年はなんと、たったの一週間でそれらをはるかに上回る
という、過去に例を見ない 「とんでもない事態」 になっているという。
さて、昨日は 「“熱中症” 予防」 の難しさについて、特に中高年層に関しては、まず
「観念や意識の問題があるのでは」 ということを述べたが、今日はさらに具体的な予防
の難しさについてである。
昨日紹介した某紙記事の 4. 「 (熱中症にかからないために) 日常生活で気をつ
けること」 によれば、
1. のどが渇いていなくても、水分をこまめに補給すること。お年寄りは脱水が進んで
ものどの渇きを覚えにくいので、特に注意が必要。
2. 汗をかいて水を飲むと血中濃度が薄くなる。体内の電解質バランスが崩れ熱中症
が進む原因となる。梅干しや塩分入りキャンディー等も必要に応じてとるようにした
い。
3. 30度以上になると発症しやすくなるので、部屋の温度を知るために寒暖計があっ
たほうがよい。エアコンや扇風機も必要以上に嫌わず上手に使うべきだ。
と紹介されている。
まず、1. についてであるが、水 (分) というのは普通、のどが渇いているからこそ
摂取したい (飲みたい) と思うわけであり、そうでないときに 「こまめに水分補給」
するにはそれなりの意識が必要である。また、いわゆる 「ビール党」 の人たちは、夏
場は夜になって飲むビール (特に1杯目) をより美味しくするために、日中の水分摂
取を極力控えようとする (かつての自分もそうだった) が、中高年になったら、そうい
う “ムチャ” は考えものということか。
次に、2. について。「体内の電解質バランス」 と言われても、素人にはなかなか難
しく、ピンとこない話である。個人的には “梅干し” ほど苦手なものはないし、また猛
暑のなか、キャンディーを口に含むのにもそれなりの覚悟?を要する人は (自分も含
めて) 少なくないのではなかろうか。
3. について。 「エアコンは嫌い」 というほどではないとしても、特に中高年の場合
は 「“効果的な活用” ができているか」 ということに大いに疑問の余地がある。その
機能を上手に使いこなせないと、逆に身体を部分的に冷やし過ぎてしまったりして別の
意味で体調を崩したり、具合が悪くなってしまうこともありうる。またこれだけ気温が高
いと、扇風機など回しても 「“熱風” が襲ってくるだけでかえって暑くなる」 などと考
えてしまうフシもある。
以上、「予防が大切」 と具体的に気をつけることを聞かされて、頭では理解できたとし
ても、実際に行動に移すのはなかなかやっかいで難しい面がある。最も大切なことは、
やはりこの連日の猛暑を 「侮らない」 ということである。ことに中高年は、「自分の若い
時分はエアコンなどなくても、また水分など大して補給しなくてもこの程度の暑さは簡単
に乗り切ったものだ」 という妙な自慢や過信を捨てて、「謙虚な気持ち?で猛暑と向き
合う」 ことが肝要であると思われる。
自分が熱中症になりかけたとき、
「果たして飼い主がちゃんと気づ
いてくれるのか」 と心配でなら
ない!? こじろう
2010年07月27日
『予防が大切』 と言われても!!!(その1)
「やっと梅雨が明けた」 と思った矢先、今度はいわゆる “猛暑” がその勢いを日に
日に増しているかのような感があり、全国各地におけるいわゆる 「熱中症」 の被害
が連日新聞紙上を賑わしている。
昨今はあたりまえのように遣われるこの 「熱中症」 という用語。少なくとも数十年前
はなじみのものではなかったように思われるし、未だ高齢者の中にはそのことば自体
を聞いたことがあっても、その意味内容まではほとんどわかっていない人も結構多い
のではなかろうか。自分はまだ (少なくとも年齢そのものは) 高齢者の仲間入りは
していないが、実を言うと、以前このことばを初めて耳にしたときは 「何かに “熱中”
しすぎてしまう症候群」 くらいにとらえてしまったことを今ここに白状するものである。
さてそれはともかく、26日の某紙朝刊で 「厳しい暑さ 熱中症の予防と対応」 と
いうタイトルの記事を目にすることとなった。その内容は、
1. 「熱中症」 の定義
2. かかりやすいのは特に 「お年寄り」 と 「こども」
3. かかりやすい環境
4. 日常生活で気をつけること
5. 危険信号
から構成されており、最後に 「熱中症はきちんと注意して正しい方法で予防さえして
いれば、絶対にかからないで済む。それだけに予防が何より大切だ」 とまとめられて
いる。たしかにその通りだが、実際にはそれがなかなか難しいのである。
というのも、先日の 「こじろう117」・・・『信じていたのに・・・』!!!(その2) でも
触れた数十年前?までの “俗説” にもみられるように、ことに中年以上の世代につ
いては、「夏は暑いのがあたりまえ」 「暑さは耐えるもの」 「心頭を滅却すれば火も
また涼し」 というような観念が (最後のはともかくとして) まだ根強く残っている面
もあるからだ。
さらにそういう観念的なことにとどまらない具体的な 「熱中症予防の難しさ」 につ
いては、「こじろう117」・・・『予防が大切』 といわれても!!!(その2) で触れる
ことにしたい。
つい先日、大嫌いな 「予防接種」 を
受けたが、「その痛さのわりに、どの程度
の効果があるのか」 について、今一つ
懐疑的な!? こじろう
日に増しているかのような感があり、全国各地におけるいわゆる 「熱中症」 の被害
が連日新聞紙上を賑わしている。
昨今はあたりまえのように遣われるこの 「熱中症」 という用語。少なくとも数十年前
はなじみのものではなかったように思われるし、未だ高齢者の中にはそのことば自体
を聞いたことがあっても、その意味内容まではほとんどわかっていない人も結構多い
のではなかろうか。自分はまだ (少なくとも年齢そのものは) 高齢者の仲間入りは
していないが、実を言うと、以前このことばを初めて耳にしたときは 「何かに “熱中”
しすぎてしまう症候群」 くらいにとらえてしまったことを今ここに白状するものである。
さてそれはともかく、26日の某紙朝刊で 「厳しい暑さ 熱中症の予防と対応」 と
いうタイトルの記事を目にすることとなった。その内容は、
1. 「熱中症」 の定義
2. かかりやすいのは特に 「お年寄り」 と 「こども」
3. かかりやすい環境
4. 日常生活で気をつけること
5. 危険信号
から構成されており、最後に 「熱中症はきちんと注意して正しい方法で予防さえして
いれば、絶対にかからないで済む。それだけに予防が何より大切だ」 とまとめられて
いる。たしかにその通りだが、実際にはそれがなかなか難しいのである。
というのも、先日の 「こじろう117」・・・『信じていたのに・・・』!!!(その2) でも
触れた数十年前?までの “俗説” にもみられるように、ことに中年以上の世代につ
いては、「夏は暑いのがあたりまえ」 「暑さは耐えるもの」 「心頭を滅却すれば火も
また涼し」 というような観念が (最後のはともかくとして) まだ根強く残っている面
もあるからだ。
さらにそういう観念的なことにとどまらない具体的な 「熱中症予防の難しさ」 につ
いては、「こじろう117」・・・『予防が大切』 といわれても!!!(その2) で触れる
ことにしたい。
つい先日、大嫌いな 「予防接種」 を
受けたが、「その痛さのわりに、どの程度
の効果があるのか」 について、今一つ
懐疑的な!? こじろう
2010年07月26日
『赤キップ』 続出!!!
昨日の某紙朝刊の中に 「ブレーキなし・危険運転・・・自転車にも赤キップ」 というタイトル
の記事があった。その内容は、
・・・・・福岡県警中央署は22日、福岡市天神で自転車の取締りを行い、男性会社員 (24才)
ら4人に道交法違反などの疑いで罰金を伴う交通切符 (赤キップ) を交付した。
発表によると、男性は22日午前8時15分ごろ、赤信号なのに市道交差点に進入した疑い。
このほか信号無視の男子学生 (19才) 、ブレーキのついていない競技用自転車に乗って
いた会社員 (23才)、歩行中の女性にぶつかりそうになった会社員 (23才) に同法の
通行区分違反などで赤キップを切った。 (中略)
危険走行をする自転車には、“注意” が一般的だが、同署には 「自転車のマナーが悪い」
という苦情が多数寄せられており、今後も厳しく取り締まる方針である・・・・・
というものである。
すでに数年前から、悪質な自転車走行などに対していわゆる 「赤キップ」 が切られると
いう報道を耳にしてはいたが、個人的にはそれはレアケースだと思っていたので、今回の
ように短時間でしかも同一署によって一気に数件の取締りが行なわれたことに、記事を読
んだ瞬間、驚きを隠すことはできなかった。
自分自身は最近自転車に乗る機会はまずありえないが、今思えば以前、その際に必ずしも
法規を完全に遵守していたとは言い難いし、また周囲の通行者などに十二分な配慮をもっ
て走行していたかといわれれば、自信をもって 「そうだ」 とは言い切れないことも事実で
ある。その理由の大きなものの一つとして、たとえば 「自転車による信号無視の一つくら
いでまさか “取締り” の対象となることはないだろう、“注意・警告” がせいぜいだろう」
と高を括っていたことがあるかもしれない。
したがって昨今自転車による重大事故などが頻繁に起きたり、自転車走行の関するマナー
が大きく社会問題化しているなか、今回の報道のような動きが加速していくことに大きな意
義や効果があることに疑いはない。
しかし逆に自分が今自転車に乗る機会がないからということを背景にして、「一方的に自転
車走行のマナーのヒドさだけをやり玉に挙げ、悪者に仕立てあげる風潮」 はやはり筋違い
である。法規を遵守し、周囲に迷惑のかからないように十分に配慮して自転車走行をしてい
る人たちにとっては、「同じ車線を走る自動車による、『非常識で自分本位で乱暴な運転』
に脅威や恐怖を感じたり、『数人で横一列にならんだままおしゃべりに夢中になって道をふ
さいでいる歩行者?』 により、走行を邪魔され迷惑している」 こともあるからだ。
誰でも自分の立場でものを考えるのは当然であるが、「立場が異なればそれぞれの事情や
主張、言い分も異なる」 のもまた事実である。公道の使用ということでいえば自動車、軽車
両 (自転車など) 、歩行者のそれぞれが法規を遵守することはもちろんのこと、自分以外
の人の立場もよく考え、“思いやり” の精神で走行することが必要といえよう。
飼い主の 「うっかりミス」 に対し、
『赤キップ』 を切りたいと思ってい
る!? こじろう
の記事があった。その内容は、
・・・・・福岡県警中央署は22日、福岡市天神で自転車の取締りを行い、男性会社員 (24才)
ら4人に道交法違反などの疑いで罰金を伴う交通切符 (赤キップ) を交付した。
発表によると、男性は22日午前8時15分ごろ、赤信号なのに市道交差点に進入した疑い。
このほか信号無視の男子学生 (19才) 、ブレーキのついていない競技用自転車に乗って
いた会社員 (23才)、歩行中の女性にぶつかりそうになった会社員 (23才) に同法の
通行区分違反などで赤キップを切った。 (中略)
危険走行をする自転車には、“注意” が一般的だが、同署には 「自転車のマナーが悪い」
という苦情が多数寄せられており、今後も厳しく取り締まる方針である・・・・・
というものである。
すでに数年前から、悪質な自転車走行などに対していわゆる 「赤キップ」 が切られると
いう報道を耳にしてはいたが、個人的にはそれはレアケースだと思っていたので、今回の
ように短時間でしかも同一署によって一気に数件の取締りが行なわれたことに、記事を読
んだ瞬間、驚きを隠すことはできなかった。
自分自身は最近自転車に乗る機会はまずありえないが、今思えば以前、その際に必ずしも
法規を完全に遵守していたとは言い難いし、また周囲の通行者などに十二分な配慮をもっ
て走行していたかといわれれば、自信をもって 「そうだ」 とは言い切れないことも事実で
ある。その理由の大きなものの一つとして、たとえば 「自転車による信号無視の一つくら
いでまさか “取締り” の対象となることはないだろう、“注意・警告” がせいぜいだろう」
と高を括っていたことがあるかもしれない。
したがって昨今自転車による重大事故などが頻繁に起きたり、自転車走行の関するマナー
が大きく社会問題化しているなか、今回の報道のような動きが加速していくことに大きな意
義や効果があることに疑いはない。
しかし逆に自分が今自転車に乗る機会がないからということを背景にして、「一方的に自転
車走行のマナーのヒドさだけをやり玉に挙げ、悪者に仕立てあげる風潮」 はやはり筋違い
である。法規を遵守し、周囲に迷惑のかからないように十分に配慮して自転車走行をしてい
る人たちにとっては、「同じ車線を走る自動車による、『非常識で自分本位で乱暴な運転』
に脅威や恐怖を感じたり、『数人で横一列にならんだままおしゃべりに夢中になって道をふ
さいでいる歩行者?』 により、走行を邪魔され迷惑している」 こともあるからだ。
誰でも自分の立場でものを考えるのは当然であるが、「立場が異なればそれぞれの事情や
主張、言い分も異なる」 のもまた事実である。公道の使用ということでいえば自動車、軽車
両 (自転車など) 、歩行者のそれぞれが法規を遵守することはもちろんのこと、自分以外
の人の立場もよく考え、“思いやり” の精神で走行することが必要といえよう。
飼い主の 「うっかりミス」 に対し、
『赤キップ』 を切りたいと思ってい
る!? こじろう
2010年07月25日
『信じていたのに・・・』!!!(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・『信じていたのに』!!!・・・(その1) の続きである。
昨日とりあげた 「頭髪に関する俗説や迷信を信じていて裏切られた?」 ところで、
とりたててどうということはない (イヤ、中には “深刻な人” もいるかもしれない) と
思われる。しかし、“生命の維持” や “身体の安全確保” を 「脅かす」 ような俗説
や迷信にとらわれていた例もかつては少なくないので、今さらながら恐ろしくなってしま
うことがある。
今から数十年前?までは、「運動中に水を飲んではいけない」 ということが一般的
に言われていた。中学生時野球部に属していた自分も、夏の炎天下でも練習中には
一切水を飲むことを禁じられていて、ときには目まいを起こしたり、気が遠くなるような
思いをしたおぼえがある。また数時間に及ぶ練習が終わるやいなや、身体から失わ
れた水分を一気に取り戻すべく、水飲み場に向かって競走でダッシュし、水道から出
る “生ぬるい” 水でも、「こんなにありがたいものがあるのか」 という気持ちで、浴
びるように飲んだものであるが、今思えば、自分も含め周囲のメンバーが熱中症など
でよく倒れなかったものだと不思議でならない。「運動中に水を飲むと余計に (汗をか
いて) 疲れる」 などというのはとんでもない迷信であるが、当時は指導者も含めそれ
をごくあたりまえのことと信じ切っていたということだろう。現在、運動中の十分な水分
補給は “常識中の常識” で当時とは正反対である。
やはり夏の話でいえば、当時は 「なるべく日焼けしておけば身体が健康になり、秋か
ら冬にかけて “カゼ” をひきにくくなる」 などという俗説が、やはり 「まことしやかに」
囁かれたものである。学校の夏休みが終わって登校した初日には、クラスで 「夏休み
日焼けコンテスト」 などというものが開催され、休み中は競って日焼けに勤しんだもの
であるが、これも今の時代では言語道断ということになるだろう。
上記のように、その時ばかりでなく将来にわたって身体などに悪影響を及ぼすようなも
のは論外であり、また逆効果となるようなものも考えものであるが、“俗説” といえども
なかにはそれほど目くじらを立てる必要のないものもあれば、当たり障りのほとんどな
い “迷信” が数多く存在することもまた事実である。またその “俗説” や “迷信”
のおかげで 「精神的に救われることになる」 などということもよくあるわけで、人生
というものはさようになかなか複雑なものといえるのだ。
連日の猛暑の中、水分の補給に
余念のない!? こじろう
昨日とりあげた 「頭髪に関する俗説や迷信を信じていて裏切られた?」 ところで、
とりたててどうということはない (イヤ、中には “深刻な人” もいるかもしれない) と
思われる。しかし、“生命の維持” や “身体の安全確保” を 「脅かす」 ような俗説
や迷信にとらわれていた例もかつては少なくないので、今さらながら恐ろしくなってしま
うことがある。
今から数十年前?までは、「運動中に水を飲んではいけない」 ということが一般的
に言われていた。中学生時野球部に属していた自分も、夏の炎天下でも練習中には
一切水を飲むことを禁じられていて、ときには目まいを起こしたり、気が遠くなるような
思いをしたおぼえがある。また数時間に及ぶ練習が終わるやいなや、身体から失わ
れた水分を一気に取り戻すべく、水飲み場に向かって競走でダッシュし、水道から出
る “生ぬるい” 水でも、「こんなにありがたいものがあるのか」 という気持ちで、浴
びるように飲んだものであるが、今思えば、自分も含め周囲のメンバーが熱中症など
でよく倒れなかったものだと不思議でならない。「運動中に水を飲むと余計に (汗をか
いて) 疲れる」 などというのはとんでもない迷信であるが、当時は指導者も含めそれ
をごくあたりまえのことと信じ切っていたということだろう。現在、運動中の十分な水分
補給は “常識中の常識” で当時とは正反対である。
やはり夏の話でいえば、当時は 「なるべく日焼けしておけば身体が健康になり、秋か
ら冬にかけて “カゼ” をひきにくくなる」 などという俗説が、やはり 「まことしやかに」
囁かれたものである。学校の夏休みが終わって登校した初日には、クラスで 「夏休み
日焼けコンテスト」 などというものが開催され、休み中は競って日焼けに勤しんだもの
であるが、これも今の時代では言語道断ということになるだろう。
上記のように、その時ばかりでなく将来にわたって身体などに悪影響を及ぼすようなも
のは論外であり、また逆効果となるようなものも考えものであるが、“俗説” といえども
なかにはそれほど目くじらを立てる必要のないものもあれば、当たり障りのほとんどな
い “迷信” が数多く存在することもまた事実である。またその “俗説” や “迷信”
のおかげで 「精神的に救われることになる」 などということもよくあるわけで、人生
というものはさようになかなか複雑なものといえるのだ。
連日の猛暑の中、水分の補給に
余念のない!? こじろう
2010年07月24日
『信じていたのに・・・』!!!(その1)
以前から 「まことしやかに」 「さもありなん」 あるいは 「あたりまえのこと」 として
言い伝えられ、信じてきたことが、実は 「科学的 (医学的) 根拠に乏しい “俗説”
であったり、“迷信” にすぎなかった」 とある日突然気づかされることはそれほど珍し
いことではない。
ことに男性にとって関心の高い “頭髪” にまつわることなどは、そういった話題?に
事欠かないものであるが、自分自身としても長い間信じて疑わなかったことが実際は
単なる俗説や迷信であることを、23日の某紙朝刊の 「頭髪のウソ・ホント 専門医
に聞く」 というタイトルの記事で思い知らされることとなった。
その記事に取り上げられている俗説で代表的なものをピックアップしてみると、
<海藻を食べると髪の毛が増える>
これは子どものころから、家庭内の食事で海藻を目にする度に親から言い続けられてき
たことであるとともに、学校の給食のメニューに海藻などが入っていたりすると必ずといっ
ていいほど話題になったものである。自分自身も長いことそう考えて疑わず、将来に備え
て?積極的に海藻を口に入れてきたつもりであったが、記事によると
「これも都市伝説の一つ。海藻類に含まれるミネラルなどは髪だけでなく身体にも良いが
絶対的に髪を増やすというものではない。髪の太さや濃さにも関係ない」
と却下されてしまっている。
<帽子をかぶるとはげやすい>
子どもの頃は、ことに今のような夏場に外に出るときは必ず帽子をかぶらされた反面、それ
なりの年齢に達して以降は、たしかに帽子をかぶると蒸れやすく頭髪によくないという話を
耳にすることが多くあり、たとえ日差しが強いような時でも躊躇するようなこともあった。
しかし記事によると、
「(帽子をかぶることで) 蒸れたり、締め付けたりするのがよくないという人もいるが、頭皮
に影響するほどではない。逆に長時間何もかぶらないで外にいると、紫外線による悪影響
の方が大きい。長時間外に出るときは帽子を着用した方が頭皮にも良い」
ということで、日射病などの予防もさることながら結局帽子をかぶった方がむしろ 「はげに
くい」 というのが専門家の見解である。
その他の例としては <頭皮の地肌が硬いとはげやすい> という俗説には 「全くナンセ
ンス。医学的な基準が全くない。血流を良くするとして頭皮をマッサージするのは気休めに
すぎず、やめてほしい」。また <頭皮の脂が毛穴に詰まるとはげやすい> というものに
は 「毛穴の状態を拡大して見せて、こんなに汚れていると不安にさせてシャンプーや施術
を売る民間療法があるが、頭の脂が抜け毛の根源みたいな言い方をするのは間違いだ。
脂は乾燥を防ぐために毛穴から出るもので、とりすぎると逆に分泌量が多くなる可能性が
ある」 などとまさに一刀両断されている。
以上のほかにも、たとえそれが一時的なものであったとしても自分自身が 「信じ込んで
いたもの」 が結局何の意味もないどころかむしろ逆効果だとわかれば、それはそれで
悲しいことである。さらに頭髪関係以外におけるさまざまな俗説や迷信と日常生活のかか
わりについては、「こじろう117」・・・『信じていたのに・・・』!!!(その2)・・・のなかで
触れてみたいと思う。
俗説や迷信を信じ込んでいる飼い主を
冷やかな目で眺めている!? こじろう
言い伝えられ、信じてきたことが、実は 「科学的 (医学的) 根拠に乏しい “俗説”
であったり、“迷信” にすぎなかった」 とある日突然気づかされることはそれほど珍し
いことではない。
ことに男性にとって関心の高い “頭髪” にまつわることなどは、そういった話題?に
事欠かないものであるが、自分自身としても長い間信じて疑わなかったことが実際は
単なる俗説や迷信であることを、23日の某紙朝刊の 「頭髪のウソ・ホント 専門医
に聞く」 というタイトルの記事で思い知らされることとなった。
その記事に取り上げられている俗説で代表的なものをピックアップしてみると、
<海藻を食べると髪の毛が増える>
これは子どものころから、家庭内の食事で海藻を目にする度に親から言い続けられてき
たことであるとともに、学校の給食のメニューに海藻などが入っていたりすると必ずといっ
ていいほど話題になったものである。自分自身も長いことそう考えて疑わず、将来に備え
て?積極的に海藻を口に入れてきたつもりであったが、記事によると
「これも都市伝説の一つ。海藻類に含まれるミネラルなどは髪だけでなく身体にも良いが
絶対的に髪を増やすというものではない。髪の太さや濃さにも関係ない」
と却下されてしまっている。
<帽子をかぶるとはげやすい>
子どもの頃は、ことに今のような夏場に外に出るときは必ず帽子をかぶらされた反面、それ
なりの年齢に達して以降は、たしかに帽子をかぶると蒸れやすく頭髪によくないという話を
耳にすることが多くあり、たとえ日差しが強いような時でも躊躇するようなこともあった。
しかし記事によると、
「(帽子をかぶることで) 蒸れたり、締め付けたりするのがよくないという人もいるが、頭皮
に影響するほどではない。逆に長時間何もかぶらないで外にいると、紫外線による悪影響
の方が大きい。長時間外に出るときは帽子を着用した方が頭皮にも良い」
ということで、日射病などの予防もさることながら結局帽子をかぶった方がむしろ 「はげに
くい」 というのが専門家の見解である。
その他の例としては <頭皮の地肌が硬いとはげやすい> という俗説には 「全くナンセ
ンス。医学的な基準が全くない。血流を良くするとして頭皮をマッサージするのは気休めに
すぎず、やめてほしい」。また <頭皮の脂が毛穴に詰まるとはげやすい> というものに
は 「毛穴の状態を拡大して見せて、こんなに汚れていると不安にさせてシャンプーや施術
を売る民間療法があるが、頭の脂が抜け毛の根源みたいな言い方をするのは間違いだ。
脂は乾燥を防ぐために毛穴から出るもので、とりすぎると逆に分泌量が多くなる可能性が
ある」 などとまさに一刀両断されている。
以上のほかにも、たとえそれが一時的なものであったとしても自分自身が 「信じ込んで
いたもの」 が結局何の意味もないどころかむしろ逆効果だとわかれば、それはそれで
悲しいことである。さらに頭髪関係以外におけるさまざまな俗説や迷信と日常生活のかか
わりについては、「こじろう117」・・・『信じていたのに・・・』!!!(その2)・・・のなかで
触れてみたいと思う。
俗説や迷信を信じ込んでいる飼い主を
冷やかな目で眺めている!? こじろう
2010年07月23日
『釈然としない』 電話!!!(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・『釈然としない』 電話!!!(その1)・・・の続きである。
国内某最大手保険会社の女性担当者からの電話で、「釈然としない」ものが残った
第2の点は 「いずれにしてもここで 『送った』 とか 『受け取っていない』 と言って
も “水かけ論” になるので、書類を作成し直してもう一度送ります」 という趣旨の
先方の言い分である。
一般的に物事には “お互いの言い分” というものが存在するのは常であるが、今回
は、根本的にそれとは性質を異にする場面である。というのも、先方から 「書類を送り
ますから署名捺印などして送りかえしてください」 と一方的に依頼されたもので、す
なわちそれは 「書類を受け取ること」 に関し本来当方がその責任や義務を負わされ
る必要のないものだからである。
したがって、先方の 「“水かけ論” になる」 という趣旨の部分は、送られ協力する
側 (今回の場合は当方) が言うのならまだしも、その逆では全く筋が通らぬ話なの
である。しかも後で詳しく家内に聞いたところでは 「これ以上いろいろ言っても仕方
ないので、自分の所属長 (所長?支社長?) に 『わざわざお願い』 してもう一
度書類を作成する」 というニュアンスがその言い分の中に含まれていたという。当
方として、その組織の中で部下と上司の間にどのような 「お願い」 があろうとなん
ら関係のない話である。そもそもこちらには全くメリットのないことを依頼され、あくま
でも協力しようとしている姿勢に対し、あまりに失礼で自分本位な態度ではないだろ
うか。
直接電話を受けた家内によれば、言葉遣いこそぞんざいなものではなかったようであ
るが、少なくとも 「お願いする」 という姿勢は終始感じられず、それどころか (書類
を再発行するなど) 「面倒なことをわざわざしてあげる」 という雰囲気を伝えてくる
ものだったという。
官公署のいわゆる “お役所仕事” でも、以前と比較して最近は徐々に改善されてき
たところがあるなか、純然たる民間会社、それもいわゆるその業界のリーディングカン
パニーを自認する超大手企業の対応としてはあまりに “お粗末” であると実感した
次第である。
今回の件は “業務” に限らず、日常生活のさまざまな場面で 「反面教師」 とする
ことができるものをいくつか含んでいるといえよう。「『今、自らがどういう立場や状況
におかれているか』 を常に的確に認識できているか」 「相手の人に、『本来はする
必要のないこと』 をしていただいているにもかかわらず、それをあたりまえのことだ
と考えていないか」 など、自分自身として普段の行動を振り返り反省するよい機会に
なったと考えるのが賢明というものであるかもしれない。
飼い主との間で 「オヤツをあげた」
「いや、まだもらっていない」 という
“水かけ論” をいつも展開している
!? こじろう
国内某最大手保険会社の女性担当者からの電話で、「釈然としない」ものが残った
第2の点は 「いずれにしてもここで 『送った』 とか 『受け取っていない』 と言って
も “水かけ論” になるので、書類を作成し直してもう一度送ります」 という趣旨の
先方の言い分である。
一般的に物事には “お互いの言い分” というものが存在するのは常であるが、今回
は、根本的にそれとは性質を異にする場面である。というのも、先方から 「書類を送り
ますから署名捺印などして送りかえしてください」 と一方的に依頼されたもので、す
なわちそれは 「書類を受け取ること」 に関し本来当方がその責任や義務を負わされ
る必要のないものだからである。
したがって、先方の 「“水かけ論” になる」 という趣旨の部分は、送られ協力する
側 (今回の場合は当方) が言うのならまだしも、その逆では全く筋が通らぬ話なの
である。しかも後で詳しく家内に聞いたところでは 「これ以上いろいろ言っても仕方
ないので、自分の所属長 (所長?支社長?) に 『わざわざお願い』 してもう一
度書類を作成する」 というニュアンスがその言い分の中に含まれていたという。当
方として、その組織の中で部下と上司の間にどのような 「お願い」 があろうとなん
ら関係のない話である。そもそもこちらには全くメリットのないことを依頼され、あくま
でも協力しようとしている姿勢に対し、あまりに失礼で自分本位な態度ではないだろ
うか。
直接電話を受けた家内によれば、言葉遣いこそぞんざいなものではなかったようであ
るが、少なくとも 「お願いする」 という姿勢は終始感じられず、それどころか (書類
を再発行するなど) 「面倒なことをわざわざしてあげる」 という雰囲気を伝えてくる
ものだったという。
官公署のいわゆる “お役所仕事” でも、以前と比較して最近は徐々に改善されてき
たところがあるなか、純然たる民間会社、それもいわゆるその業界のリーディングカン
パニーを自認する超大手企業の対応としてはあまりに “お粗末” であると実感した
次第である。
今回の件は “業務” に限らず、日常生活のさまざまな場面で 「反面教師」 とする
ことができるものをいくつか含んでいるといえよう。「『今、自らがどういう立場や状況
におかれているか』 を常に的確に認識できているか」 「相手の人に、『本来はする
必要のないこと』 をしていただいているにもかかわらず、それをあたりまえのことだ
と考えていないか」 など、自分自身として普段の行動を振り返り反省するよい機会に
なったと考えるのが賢明というものであるかもしれない。
飼い主との間で 「オヤツをあげた」
「いや、まだもらっていない」 という
“水かけ論” をいつも展開している
!? こじろう
2010年07月22日
『釈然としない』 電話!!!(その1)
今月初め、国内某大手保険会社営業所の女性事務担当者より 「(ある) 手続きの
ために速達で書類を送るので、署名・捺印などして送りかえしてほしい」 旨の電話
が自宅にあったことを家内から聞いていた。すでに2~3週間前のことであり、しか
も先方からの一方的な依頼によるものということもあって、家内ともどもその後、特に
気にも留めずにいたところ、昨日また同じ女性担当者から電話が入ったという。
その際の先方と当方 (家内) の電話での大まかなやりとりは、
<先方> 「先日電話して送った書類、大事なものなので早く返送してほしいので
すが」
<当方> 「まだ書類が届いていないんですけど」
<先方> 「もうだいぶ以前に速達で送ったんですが」
<当方> 「といわれても、届いていないんですが」
<先方> 「こちらには 『送ったという記録』 が残っているんですけど」
<当方> 「書留で送っていただいたんですか」
<先方> 「いいえ、普通の (速達) 郵便です」
<当方> 「ああ、そうなんですか」
<先方> 「いずれにしても 『送った』 とか 『受け取っていない』 といっても
“水かけ論” になるので、書類を作成し直してもう一度送り直します」
<当方> 「わかりました。お願いします」
というようなものであったという。
今回の用件は一旦それで終えたとして、直接電話を受けた家内にとって、および後
でこのやり取りの内容を聞いた自分にとって、何か 「釈然としないもの」 が残った
のは事実である。
まず第一に、「こちらには 『送ったという記録』 が残っているんですけど」 という
先方の言い分である。「記録」 といっても、それはたとえば書留郵便の “受取票”
というようなものでないことは会話の中で明らかにされている。また仮にそういう公的
な?ものであったとしても、それはあくまでも先方 (送る側) と郵便事業者との間
のやりとりに過ぎず、当方 (送られる側) にはなんら関係のないことである。まして
今回先方のいう 「記録」 とはその組織内のルールに従って?事務処理上いわば
勝手につけている 「記録」 であり、それを (外部の人間である) 当方に伝えられ
てもどうしようもないことである。したがって 「こちらには 『送った記録』 があるんで
すけど」 という言い分は相手側 (今回でいえば当方) にとって全く意味をなさない
どころか、聞きようによっては 「相手方に責任を転嫁させようとしている」 あるいは
百歩譲っても、「自分には落ち度はない」 ということをただ単に主張したいだけとし
か思えないだろう。しかも今回の件はもともと当方から連絡をとったものでは一切な
く、先方から一方的に依頼されていることなのである。
さらに第二の 「釈然としない点」 および全般的な顧客対応の問題点については、
明日の 「こじろう117」 でこの続きとして触れることにしたい。
飼い主が自分にオヤツを渡すのを忘れない
ように 「記録をつけておいてほしい」 と
願っている!? こじろう
ために速達で書類を送るので、署名・捺印などして送りかえしてほしい」 旨の電話
が自宅にあったことを家内から聞いていた。すでに2~3週間前のことであり、しか
も先方からの一方的な依頼によるものということもあって、家内ともどもその後、特に
気にも留めずにいたところ、昨日また同じ女性担当者から電話が入ったという。
その際の先方と当方 (家内) の電話での大まかなやりとりは、
<先方> 「先日電話して送った書類、大事なものなので早く返送してほしいので
すが」
<当方> 「まだ書類が届いていないんですけど」
<先方> 「もうだいぶ以前に速達で送ったんですが」
<当方> 「といわれても、届いていないんですが」
<先方> 「こちらには 『送ったという記録』 が残っているんですけど」
<当方> 「書留で送っていただいたんですか」
<先方> 「いいえ、普通の (速達) 郵便です」
<当方> 「ああ、そうなんですか」
<先方> 「いずれにしても 『送った』 とか 『受け取っていない』 といっても
“水かけ論” になるので、書類を作成し直してもう一度送り直します」
<当方> 「わかりました。お願いします」
というようなものであったという。
今回の用件は一旦それで終えたとして、直接電話を受けた家内にとって、および後
でこのやり取りの内容を聞いた自分にとって、何か 「釈然としないもの」 が残った
のは事実である。
まず第一に、「こちらには 『送ったという記録』 が残っているんですけど」 という
先方の言い分である。「記録」 といっても、それはたとえば書留郵便の “受取票”
というようなものでないことは会話の中で明らかにされている。また仮にそういう公的
な?ものであったとしても、それはあくまでも先方 (送る側) と郵便事業者との間
のやりとりに過ぎず、当方 (送られる側) にはなんら関係のないことである。まして
今回先方のいう 「記録」 とはその組織内のルールに従って?事務処理上いわば
勝手につけている 「記録」 であり、それを (外部の人間である) 当方に伝えられ
てもどうしようもないことである。したがって 「こちらには 『送った記録』 があるんで
すけど」 という言い分は相手側 (今回でいえば当方) にとって全く意味をなさない
どころか、聞きようによっては 「相手方に責任を転嫁させようとしている」 あるいは
百歩譲っても、「自分には落ち度はない」 ということをただ単に主張したいだけとし
か思えないだろう。しかも今回の件はもともと当方から連絡をとったものでは一切な
く、先方から一方的に依頼されていることなのである。
さらに第二の 「釈然としない点」 および全般的な顧客対応の問題点については、
明日の 「こじろう117」 でこの続きとして触れることにしたい。
飼い主が自分にオヤツを渡すのを忘れない
ように 「記録をつけておいてほしい」 と
願っている!? こじろう
2010年07月21日
『一瞬のスキ』 も許されない!!!
20日某紙朝刊に、「3連休の最終日である19日、海や川などの水難事故により、全
国で6人が死亡、5人が意識不明の重体、1人が行方不明」 というタイトルの記事が
掲載された。毎年この時期になると、ほぼ同様の報道を目にするのが恒例になって
しまっているのは本当に残念で悲しいことである。
一口に水難事故といっても事故それぞれの原因があり、状況もさまざまであるため、
一概にいえることではないが、ことに心が痛むのが小学校低学年くらいまでの幼児
らが犠牲になるケースである。19日だけでも 「神奈川で6才の男児が川で流され
死亡」 「福岡の用水路でおぼれた4歳の男児が心肺停止」 「東京・大阪のそれぞれ
の川で小学生が重体」 と発表されている。
大人はもちろん、一般的には子どもでも小学校高学年以上になれば一応 「何をどう
すれば危険であるか」 は予見・判断することのできる可能性は高いだろう。しかし
それを乳幼児に期待するのは普通に考えて無理な話である。つまり、そういう子ども
たちの生命・身体の安全の確保は100%周囲の大人たち、特に親・保護者の責任と
いえるのである。小さな子どもというのはほんの一瞬でも目を離したスキにとんでも
ないこと、大人では到底考えつかないことをするものだと普段から考えておくべきで、
海や川に限らず、一歩外に出た以上は絶対にその行動から目だけでなく身体を離す
ことも許されないのである。
昨日たまたま市街地の大きな通りを自動車で走行中のこと、歩道上であるとはいえ、
まだ “ヨチヨチ歩き” の子どもが、(父親と思われる) 若い男性から5~6mくらい
離れて立っているのを目にすることがあった。自動車の往来の激しい道路までその子
の歩幅をもってしてもほんの数歩ほどという距離である。もし、そのまま路上に足を
踏み出して走行中の自動車に接触でもしたらまさにひとたまりもないというところで
あろう。本当にヒヤリとする瞬間であった。
事故というものはほんの一瞬で起きてしまうが、そこから生ずる痛み、苦しみ、悩み
などは事故に遭った当人のみならず周囲の人々にとって途切れなく一生続く可能性
が高いのである。特に小さな子どもが事故に遭う場合はその親、保護者にとってはで
きることなら自分がその痛みや苦しみを代わりに背負いたいくらいのものであろう。人
生のいろいろな場面に後悔はつきものであるが、この手の後悔、つまりたとえ一瞬で
も小さな子どもから目を離したことで起きてしまった事故についての後悔は絶対に避
けたいものである。
(「こじろう117」・・・『ヒヤリ』とする瞬間多発(その3)・・・参照)
飼い主が一瞬目を離したスキに、
“とんでもないこと” をしでかす
可能性のある!? こじろう
国で6人が死亡、5人が意識不明の重体、1人が行方不明」 というタイトルの記事が
掲載された。毎年この時期になると、ほぼ同様の報道を目にするのが恒例になって
しまっているのは本当に残念で悲しいことである。
一口に水難事故といっても事故それぞれの原因があり、状況もさまざまであるため、
一概にいえることではないが、ことに心が痛むのが小学校低学年くらいまでの幼児
らが犠牲になるケースである。19日だけでも 「神奈川で6才の男児が川で流され
死亡」 「福岡の用水路でおぼれた4歳の男児が心肺停止」 「東京・大阪のそれぞれ
の川で小学生が重体」 と発表されている。
大人はもちろん、一般的には子どもでも小学校高学年以上になれば一応 「何をどう
すれば危険であるか」 は予見・判断することのできる可能性は高いだろう。しかし
それを乳幼児に期待するのは普通に考えて無理な話である。つまり、そういう子ども
たちの生命・身体の安全の確保は100%周囲の大人たち、特に親・保護者の責任と
いえるのである。小さな子どもというのはほんの一瞬でも目を離したスキにとんでも
ないこと、大人では到底考えつかないことをするものだと普段から考えておくべきで、
海や川に限らず、一歩外に出た以上は絶対にその行動から目だけでなく身体を離す
ことも許されないのである。
昨日たまたま市街地の大きな通りを自動車で走行中のこと、歩道上であるとはいえ、
まだ “ヨチヨチ歩き” の子どもが、(父親と思われる) 若い男性から5~6mくらい
離れて立っているのを目にすることがあった。自動車の往来の激しい道路までその子
の歩幅をもってしてもほんの数歩ほどという距離である。もし、そのまま路上に足を
踏み出して走行中の自動車に接触でもしたらまさにひとたまりもないというところで
あろう。本当にヒヤリとする瞬間であった。
事故というものはほんの一瞬で起きてしまうが、そこから生ずる痛み、苦しみ、悩み
などは事故に遭った当人のみならず周囲の人々にとって途切れなく一生続く可能性
が高いのである。特に小さな子どもが事故に遭う場合はその親、保護者にとってはで
きることなら自分がその痛みや苦しみを代わりに背負いたいくらいのものであろう。人
生のいろいろな場面に後悔はつきものであるが、この手の後悔、つまりたとえ一瞬で
も小さな子どもから目を離したことで起きてしまった事故についての後悔は絶対に避
けたいものである。
(「こじろう117」・・・『ヒヤリ』とする瞬間多発(その3)・・・参照)
飼い主が一瞬目を離したスキに、
“とんでもないこと” をしでかす
可能性のある!? こじろう
2010年07月20日
“危険?” な 『見出し』!!!(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・“危険?” な 『見出し』!!!(その1)・・・の続きである。
今の日本相撲協会および貴乃花親方を個人的に擁護するつもりは特別ないし、これまで
の悪習を完全に立ち切るためにもここはどんな些細なことでも徹底的に追及する姿勢が、
協会内部のみならず新聞社をはじめとするメディアにも必要であろう。しかし、だからと
いって、事実の検証や確証のないままに一般に 「一方的なイメージ」 を抱かせ、先入
観を植えつけるるような報道が許されるものではない。
17日の記事における本文を読む限り、県警の見解のとおり 「親方が中学生の両親らと
食事をしていた少なくともその同じ “場所” (店内) に暴力関係者が存在した」 という
のはおそらく事実であろうと推測される。しかし、それはあくまでも “その場に” という
ことにすぎず、“同席” ということが確認されたものではない。またたとえ “同席” で
あったとしても、それは (暴力団関係者であるということを) “認識した同席” なのか、
“偶然の同席” なのかはこの時点の県警の発表では断定できないものである。問題と
なる、読み手の関心のある部分はまさにそこのところ、つまり親方が暴力団関係者がそ
の場にいることをあらかじめ認識していたかどうかなのである。今回の記事の見出しでは
その最も肝心なところが 「貴乃花親方が暴力団と同席」 という表現になっており、そ
こにはすでに “偶然の同席” ではないというニュアンスが含まれているのは否定でき
ないであろう。本文を読めば貴乃花親方が “認識した同席” であることを即座に否定
していることはわかるが、昨日も述べたように、読者の中には 「見出し」 の文字だけ
をもってその事件の本質をイメージしてしまう人もそれなりにいるだろうし、よしんば本
文に一通り目を配したとしても、「見出し」 のインパクトが強ければ強いほどそれが大
きな先入観となって全体的な内容の把握に影響を及ぼす可能性も高いのである。
記事の書き手側としては、その出来いかんが読み手のその記事に対する興味を左右
する、つまり本文自体を読んでもらえるかに直結するほど重要となるのが 「見出し」 で
あり、いかに瞬間的に強いインパクトを与えられるかに執心するのはいたし方ないことで
あろう。しかしあくまでも本来それは記事の入り口にすぎないものである。
外にある看板だけが立派で目を引くものであっても、中身が伴わないレストランはやはり
客には支持されないだろうし、何よりも裏切りである。それでも飲食店などは結局そのツケ
を払わされるのは自店自身であるが、報道機関には 「正確な情報の提供」 という何より
にも優先される社会的使命が存在するのである。
また報道機関の姿勢もさることながら、見出しはもちろんのことその記事本文についても
決して鵜呑みにせず、理性的客観的判断を下すのが読み手側の責任というものである。
(「こじろう117」・・・『鵜呑み』 にしてはいけない・・・参照)
飼い主がした約束を決して鵜呑みに
せず、常に警戒の姿勢を崩すことの
ない!? こじろう
今の日本相撲協会および貴乃花親方を個人的に擁護するつもりは特別ないし、これまで
の悪習を完全に立ち切るためにもここはどんな些細なことでも徹底的に追及する姿勢が、
協会内部のみならず新聞社をはじめとするメディアにも必要であろう。しかし、だからと
いって、事実の検証や確証のないままに一般に 「一方的なイメージ」 を抱かせ、先入
観を植えつけるるような報道が許されるものではない。
17日の記事における本文を読む限り、県警の見解のとおり 「親方が中学生の両親らと
食事をしていた少なくともその同じ “場所” (店内) に暴力関係者が存在した」 という
のはおそらく事実であろうと推測される。しかし、それはあくまでも “その場に” という
ことにすぎず、“同席” ということが確認されたものではない。またたとえ “同席” で
あったとしても、それは (暴力団関係者であるということを) “認識した同席” なのか、
“偶然の同席” なのかはこの時点の県警の発表では断定できないものである。問題と
なる、読み手の関心のある部分はまさにそこのところ、つまり親方が暴力団関係者がそ
の場にいることをあらかじめ認識していたかどうかなのである。今回の記事の見出しでは
その最も肝心なところが 「貴乃花親方が暴力団と同席」 という表現になっており、そ
こにはすでに “偶然の同席” ではないというニュアンスが含まれているのは否定でき
ないであろう。本文を読めば貴乃花親方が “認識した同席” であることを即座に否定
していることはわかるが、昨日も述べたように、読者の中には 「見出し」 の文字だけ
をもってその事件の本質をイメージしてしまう人もそれなりにいるだろうし、よしんば本
文に一通り目を配したとしても、「見出し」 のインパクトが強ければ強いほどそれが大
きな先入観となって全体的な内容の把握に影響を及ぼす可能性も高いのである。
記事の書き手側としては、その出来いかんが読み手のその記事に対する興味を左右
する、つまり本文自体を読んでもらえるかに直結するほど重要となるのが 「見出し」 で
あり、いかに瞬間的に強いインパクトを与えられるかに執心するのはいたし方ないことで
あろう。しかしあくまでも本来それは記事の入り口にすぎないものである。
外にある看板だけが立派で目を引くものであっても、中身が伴わないレストランはやはり
客には支持されないだろうし、何よりも裏切りである。それでも飲食店などは結局そのツケ
を払わされるのは自店自身であるが、報道機関には 「正確な情報の提供」 という何より
にも優先される社会的使命が存在するのである。
また報道機関の姿勢もさることながら、見出しはもちろんのことその記事本文についても
決して鵜呑みにせず、理性的客観的判断を下すのが読み手側の責任というものである。
(「こじろう117」・・・『鵜呑み』 にしてはいけない・・・参照)
飼い主がした約束を決して鵜呑みに
せず、常に警戒の姿勢を崩すことの
ない!? こじろう
2010年07月19日
“危険?” な 『見出し』!!!(その1)
新聞などの記事を読む前にはまずその 「見出し」 が目に入るのが当然であり、逆にいえ
ば記事を読んでもらえるかどうかは、いかに 「見出し」 に興味をもってもらえるかにかかっ
ているといってもいいほどである。まさに記事の “命運” を握っているともいえる、極めて
重要な役割を果たす 「見出し」 であるが、よくよく本文を読んでみると必ずしもその見出
しの内容通りになっていないことはそれほど珍しいことではない。さらにいえば、じっくりと
本文を読んでいる時間的余裕がないときなどは、その不用意な見出しによって読み手に
「事実とは異なるイメージ」 を先行・鵜呑みにさせてしまう危険すらあるように思われる。
17日某紙朝刊に 「貴乃花親方が暴力団と同席」 という見出しの記事が掲載された。一
連の賭博事件をはじめとする暴力団関係者との関わりが大きな社会問題となり、各方面
からの大きな批判の矢面に立たされている日本相撲協会にとってまさに最悪のタイミング
であり、特にこれからの協会を背負って立つべき一番手の親方に関することだけに、その
「見出し」 を目にした段階では 「もう大相撲は救いようがないな」 くらいに思った人も
少なくないのではなかろうか。
さてその本文の内容であるが、
・・・・・大相撲の貴乃花親方 (37才) が6月、新弟子の勧誘のため愛媛県愛南町を訪
れ保護者らと会食をした際、地元の暴力団関係者らが同席していたことが16日、県警へ
の取材でわかった。(中略) 貴乃花親方は名古屋場所が開催されている愛知県体育館
で報道陣に対し、「暴力団との付き合い、面識は一切ありません」 と暴力団関係者との
個人的な交際を否定、相撲協会への報告については 「まだしていない」 と述べた。
同親方によると、6月に新弟子勧誘と相撲の指導のため愛媛県を訪れ、11日夜に愛南町
で勧誘している中学生の両親ら14~5名と会食。県警らによると、相撲のけいこを見たり
食事をした場に、地元の暴力団関係者が含まれていた。
貴乃花親方は 「(一緒にいたのは) 子どもの親御さんで、そういう (暴力団) ふうに
見える人はいなかった」 と強調。現地滞在中は勧誘した中学生の父親が付き添い 「そ
の方の付き合いの中で行動した」 と話した・・・・・
というものである。
この件に関してはその後の報道でもいろいろと取りざたされているが、そのこと (この事
件そのものの本質) とともに、少なくともこの記事の内容に対し、「先の 『見出し』 が果
たして適切なものであったのか」 という検討が個人的にはまず必要であると思われる。
明日の 「こじろう117」 でこの続きとして触れてみたいと思う。
見た目で自分に対する 「イメージ」
を先行させないでほしいと常日頃
から願っている!? こじろう
ば記事を読んでもらえるかどうかは、いかに 「見出し」 に興味をもってもらえるかにかかっ
ているといってもいいほどである。まさに記事の “命運” を握っているともいえる、極めて
重要な役割を果たす 「見出し」 であるが、よくよく本文を読んでみると必ずしもその見出
しの内容通りになっていないことはそれほど珍しいことではない。さらにいえば、じっくりと
本文を読んでいる時間的余裕がないときなどは、その不用意な見出しによって読み手に
「事実とは異なるイメージ」 を先行・鵜呑みにさせてしまう危険すらあるように思われる。
17日某紙朝刊に 「貴乃花親方が暴力団と同席」 という見出しの記事が掲載された。一
連の賭博事件をはじめとする暴力団関係者との関わりが大きな社会問題となり、各方面
からの大きな批判の矢面に立たされている日本相撲協会にとってまさに最悪のタイミング
であり、特にこれからの協会を背負って立つべき一番手の親方に関することだけに、その
「見出し」 を目にした段階では 「もう大相撲は救いようがないな」 くらいに思った人も
少なくないのではなかろうか。
さてその本文の内容であるが、
・・・・・大相撲の貴乃花親方 (37才) が6月、新弟子の勧誘のため愛媛県愛南町を訪
れ保護者らと会食をした際、地元の暴力団関係者らが同席していたことが16日、県警へ
の取材でわかった。(中略) 貴乃花親方は名古屋場所が開催されている愛知県体育館
で報道陣に対し、「暴力団との付き合い、面識は一切ありません」 と暴力団関係者との
個人的な交際を否定、相撲協会への報告については 「まだしていない」 と述べた。
同親方によると、6月に新弟子勧誘と相撲の指導のため愛媛県を訪れ、11日夜に愛南町
で勧誘している中学生の両親ら14~5名と会食。県警らによると、相撲のけいこを見たり
食事をした場に、地元の暴力団関係者が含まれていた。
貴乃花親方は 「(一緒にいたのは) 子どもの親御さんで、そういう (暴力団) ふうに
見える人はいなかった」 と強調。現地滞在中は勧誘した中学生の父親が付き添い 「そ
の方の付き合いの中で行動した」 と話した・・・・・
というものである。
この件に関してはその後の報道でもいろいろと取りざたされているが、そのこと (この事
件そのものの本質) とともに、少なくともこの記事の内容に対し、「先の 『見出し』 が果
たして適切なものであったのか」 という検討が個人的にはまず必要であると思われる。
明日の 「こじろう117」 でこの続きとして触れてみたいと思う。
見た目で自分に対する 「イメージ」
を先行させないでほしいと常日頃
から願っている!? こじろう
2010年07月18日
『まさか? 実行するとは』!!!(その3)
「こじろう117」・・・『まさか? 実行するとは』!!!(その1) および (その2) の続きである。
今までも述べたように、今回の事件の特徴の一つに 「思いつくことはあったとしても、それ
を実際に行動を移すとは極めて考えにくい」 という部分があるが、これはかつてはあまり考
えられなかった現代社会特有の状況や特性と無縁ではないだろう。
それはまず現代風にいえば 「バーチャル」 と 「リアリティ」 の区別が薄れているということ
である。たとえば子どもが直接的に最も影響を受けやすいと思われる映像の世界においても、
その技術の目覚ましい進歩により以前は完全な 「作りもの」 にすぎなかったもの、そうと
しか見えなかったものが 「本物」 といっても何ら差し支えのないものに仕上がっているこ
とがある。さらに以前は少なくとも子どもの段階では到底手に入れることが困難だと思われ
るようなさまざまな情報、それもどちらかといえば健全な発育にとって好ましくない内容の
ものを容易にしかも瞬時に手に入れることもできるようにもなっている。
それらを背景に、「ここまでは 『空想や願望の世界』 ここからは 『現実の世界』 という基
準に関する認識に大人と子どもの間で大きな差異がある」 のが普通となり、大人が 「まさ
か本当にここまでしないだろう」 と考えることでも子どもは躊躇することなく実行してしまう
可能性が高くなるのである。「いや、“大人” の中にだってここでいう “子どもの基準” に
沿って行動する人はたくさんいるではないか」 という反論も存在するだろうが、そのことに
ついてはまたいずれの機会に検討したい。
今回の少女らについては、その後の週刊誌の報道などにより日常の素行にもいろいろな問
題があったとされているが、このように 「そういえばそうだった」 と関係者の証言が次から
次へと (あることないことが誇張されて) 出てくるのは、こういう事件が起きた時の常でも
ある。したがって事件の発生以前にそういうことを (件の教諭も含めて) 周囲がどの程度
認識していたかは実際のところよくわからないのである。またこういう10代の少年少女が
起こした最近の事件の多くでは、彼らに対して 「普段はおとなしく目立たなかった」 とか
「こんなことをするようにはとても見えなかった」 というようなコメントが少なくない気がする。
つまり、日常の表面的な様子や雰囲気だけでは事件の予兆を見抜くことが極めて困難に
なっているということは確実にいえるのである。
今回のテーマのもととなったのは、事件の予告を実際に耳にしていながらなんら具体的な
対処をしなかった教諭に関する報道であるが、これを単なる一教諭の姿勢の問題として非
難するのはあまりにも短絡的である。少女たちの発した “サイン” を見逃してしまったのは
いわば現代の社会全体の責任であり、また 「時代の流れだから」 「そういう時代だから」
という括り方をしてしまえば今後ますますこの手の事件は増え続けていくことだろう。
「空想・願望」 と 「現実」 との違い
を人間以上によくわかっている
つもりの!? こじろう
今までも述べたように、今回の事件の特徴の一つに 「思いつくことはあったとしても、それ
を実際に行動を移すとは極めて考えにくい」 という部分があるが、これはかつてはあまり考
えられなかった現代社会特有の状況や特性と無縁ではないだろう。
それはまず現代風にいえば 「バーチャル」 と 「リアリティ」 の区別が薄れているということ
である。たとえば子どもが直接的に最も影響を受けやすいと思われる映像の世界においても、
その技術の目覚ましい進歩により以前は完全な 「作りもの」 にすぎなかったもの、そうと
しか見えなかったものが 「本物」 といっても何ら差し支えのないものに仕上がっているこ
とがある。さらに以前は少なくとも子どもの段階では到底手に入れることが困難だと思われ
るようなさまざまな情報、それもどちらかといえば健全な発育にとって好ましくない内容の
ものを容易にしかも瞬時に手に入れることもできるようにもなっている。
それらを背景に、「ここまでは 『空想や願望の世界』 ここからは 『現実の世界』 という基
準に関する認識に大人と子どもの間で大きな差異がある」 のが普通となり、大人が 「まさ
か本当にここまでしないだろう」 と考えることでも子どもは躊躇することなく実行してしまう
可能性が高くなるのである。「いや、“大人” の中にだってここでいう “子どもの基準” に
沿って行動する人はたくさんいるではないか」 という反論も存在するだろうが、そのことに
ついてはまたいずれの機会に検討したい。
今回の少女らについては、その後の週刊誌の報道などにより日常の素行にもいろいろな問
題があったとされているが、このように 「そういえばそうだった」 と関係者の証言が次から
次へと (あることないことが誇張されて) 出てくるのは、こういう事件が起きた時の常でも
ある。したがって事件の発生以前にそういうことを (件の教諭も含めて) 周囲がどの程度
認識していたかは実際のところよくわからないのである。またこういう10代の少年少女が
起こした最近の事件の多くでは、彼らに対して 「普段はおとなしく目立たなかった」 とか
「こんなことをするようにはとても見えなかった」 というようなコメントが少なくない気がする。
つまり、日常の表面的な様子や雰囲気だけでは事件の予兆を見抜くことが極めて困難に
なっているということは確実にいえるのである。
今回のテーマのもととなったのは、事件の予告を実際に耳にしていながらなんら具体的な
対処をしなかった教諭に関する報道であるが、これを単なる一教諭の姿勢の問題として非
難するのはあまりにも短絡的である。少女たちの発した “サイン” を見逃してしまったのは
いわば現代の社会全体の責任であり、また 「時代の流れだから」 「そういう時代だから」
という括り方をしてしまえば今後ますますこの手の事件は増え続けていくことだろう。
「空想・願望」 と 「現実」 との違い
を人間以上によくわかっている
つもりの!? こじろう
2010年07月17日
『まさか? 実行するとは』!!!(その2)
「こじろう117」・・・『まさか? 実行するとは』!!!(その1)・・・の続きである。
昨日も述べたが、今回の事件のように 「自宅に放火する」 「親を殺す (刺す) 」 など
ということを14~15才の少女が話しているのを耳にしたとして、「一人の教諭の立場とし
して果たしてそれが本当に実行されると真剣に考え、事前にしかるべき対応がとれたであ
ろうか」 つまりこの事件の発生を未然に防ぐことができたかということにはやはり大いに
疑問が残る。それはこのような大それた?発想がまさか実際の行動につながるとは常識
的には考えにくいものであるのに加え、教諭の立場として一家庭内の事情に関与するこ
とに限界があるからという点も考慮しなくてはならないだろう。
今回の犯行の動機に長女の親に対する強い憎悪があったことはすでに大きく報道されて
いる事実である。家庭内における親子の関係が学校教育に及ぼす影響は当然小さくはな
いが、とはいえそれは純然たるプライベートな問題でもある。目に見える兆候 (たとえば
虐待における外傷など) があったり、以前にその生徒が非行により補導されたなどの際
に親が保護者としてまったく無責任な態度をとったことがあるなどの経緯がない限り、教
諭の立場としてその親子の日常の関係に立ち入ることには限界があるどころか、プライバ
シーの侵害にすらなる恐れがある。しかもその教諭がその長女のクラスの担任であるとし
て、相当数の家庭 (普通に考えて30人くらいにはなるだろうが) の詳しい状況をすべて
把握するのは不可能であると言わざるをえない。
生徒・児童に関する問題が起こったとき、それが学校内でのことならまだしも、なんでも
かんでも 「学校側は把握していたのか」 「学校・教諭は何をしていたのか」 というよう
に騒ぎ立てる昨今の風潮があるが、その中には本来、完全に家庭内で処理されるべきも
のが数多く含まれていることは否定できないであろう。学校・教師側が生徒・児童の家庭
内に無関心であっていいとは決して言いたくないが、学校として関与すべき領域と、あく
までも家庭内で責任をもって解決すべき基本的なことに関する領域にはそれなりの明確
な境界線があるとの認識はどうしても必要である。
以上の点などを総合的に考慮したとしてもなお、(宝塚市教委がいうように) 「少女らの
発信した “サイン” を結果として無視した」 に等しいこの教諭に一切の落ち度がなか
ったとは言い難いだろう。しかし、ことに昨今の教育現場の状況を考慮することなしに、一
方的にこの事件の発生に至る経緯を語るのは危険であることも否定できない。
あすの 「こじろう117」 ではこの件のまとめとして、こういった事件の起こる背景など
に触れてみたいと思う。
「自分の領域」 に飼い主が勝手に
立ち入ることを 「プライバシーの
侵害」 であるとして激しく抗議す
ることもある!? こじろう
昨日も述べたが、今回の事件のように 「自宅に放火する」 「親を殺す (刺す) 」 など
ということを14~15才の少女が話しているのを耳にしたとして、「一人の教諭の立場とし
して果たしてそれが本当に実行されると真剣に考え、事前にしかるべき対応がとれたであ
ろうか」 つまりこの事件の発生を未然に防ぐことができたかということにはやはり大いに
疑問が残る。それはこのような大それた?発想がまさか実際の行動につながるとは常識
的には考えにくいものであるのに加え、教諭の立場として一家庭内の事情に関与するこ
とに限界があるからという点も考慮しなくてはならないだろう。
今回の犯行の動機に長女の親に対する強い憎悪があったことはすでに大きく報道されて
いる事実である。家庭内における親子の関係が学校教育に及ぼす影響は当然小さくはな
いが、とはいえそれは純然たるプライベートな問題でもある。目に見える兆候 (たとえば
虐待における外傷など) があったり、以前にその生徒が非行により補導されたなどの際
に親が保護者としてまったく無責任な態度をとったことがあるなどの経緯がない限り、教
諭の立場としてその親子の日常の関係に立ち入ることには限界があるどころか、プライバ
シーの侵害にすらなる恐れがある。しかもその教諭がその長女のクラスの担任であるとし
て、相当数の家庭 (普通に考えて30人くらいにはなるだろうが) の詳しい状況をすべて
把握するのは不可能であると言わざるをえない。
生徒・児童に関する問題が起こったとき、それが学校内でのことならまだしも、なんでも
かんでも 「学校側は把握していたのか」 「学校・教諭は何をしていたのか」 というよう
に騒ぎ立てる昨今の風潮があるが、その中には本来、完全に家庭内で処理されるべきも
のが数多く含まれていることは否定できないであろう。学校・教師側が生徒・児童の家庭
内に無関心であっていいとは決して言いたくないが、学校として関与すべき領域と、あく
までも家庭内で責任をもって解決すべき基本的なことに関する領域にはそれなりの明確
な境界線があるとの認識はどうしても必要である。
以上の点などを総合的に考慮したとしてもなお、(宝塚市教委がいうように) 「少女らの
発信した “サイン” を結果として無視した」 に等しいこの教諭に一切の落ち度がなか
ったとは言い難いだろう。しかし、ことに昨今の教育現場の状況を考慮することなしに、一
方的にこの事件の発生に至る経緯を語るのは危険であることも否定できない。
あすの 「こじろう117」 ではこの件のまとめとして、こういった事件の起こる背景など
に触れてみたいと思う。
「自分の領域」 に飼い主が勝手に
立ち入ることを 「プライバシーの
侵害」 であるとして激しく抗議す
ることもある!? こじろう
2010年07月16日
『まさか? 実行するとは』!!!(その1)
去る9日、宝塚市で起きた中3生長女 (15才) とその友人 (14才) による自宅放火
(殺人未遂) 事件は、世間一般、特にその少女らと同年代の子をもつ親 (保護者) を
震撼させる衝撃的なものであったが、それに関する続報で、昨日興味深いニュースが地
元 (兵庫県) の某紙から配信された。
そのタイトルは 「長女の 『犯行予告』 聞いた教諭、受け流す」 というものであり、内
容は、
・・・・・宝塚市の放火事件で、殺人未遂などで兵庫県警に逮捕された市立中学校3年の
長女 (15才) と 同級生の少女 (14才) が級友に放火の予告をした際、同校教諭も
同席していたことが級友らの話でわかった。市教委によると教諭は 「『放火』 とか 『午前
2時』 いうことばは聞いておらず、家出でもするつもりかと思った」 と言い、その場で少女
らに 「あかんで」 と注意したという。
級友らによると長女は事件前日の8日、5時限目の授業に出席。一緒にいた少女と級友ら
に 「明日やる」 「午前2時に火をつける」 「親を刺す」 などと予告した。その際、授業を
していた教諭も話を聞いたが、 「まあまあ」 と受け流していたという。
(中略)
宝塚市教委は 「結果的に “サイン” を見逃した、と言われても仕方がない」 とコメント
している。・・・・・
というものである。
この記事を読んで、まず市教委のコメントは 「いかにも」 という感が否めないが、それは
ともかく、「なんだ。教師がハッキリと犯行予告?を聞いていたんじゃないか。なぜ止めな
かったんだ」 「教師の職務怠慢が招いた事件じゃないか」 などと非難・批判するのは簡
単である。しかしそういうことを言う人たちも、今回もし自分がその (教諭の) の立場に
いたとしたら、本当に真剣にその話を訊き、積極的に関与し、犯行を止めるところまでいき
ついたであろうかという疑問は大いにある。やはり後になって 「まさか?本当に実行する
とは思わなかった」 というのが本音となるのではないか。
決め手や前提になるのは、その日に至るまでのその長女の生活態度や言動などであるが、
仮に普段から 「いつそういう事件を起こしても不思議でない」 「いかにもそういう事件を
起こしそう」 という生徒だとしても、まさかまだ15才の少女が本当に自宅に放火し、まし
て真剣に親を殺そうとしているなどと “現実に” 予想し、事前に対処しろと言われても
それは難しいのではないか。一般の常識人 (少年少女を含む) であれば到底考えつ
かない、思いつかないことですらあるうえに、たとえ思いついたとしてもそれをイザ実行に
移すとなれば、これはもうドラマや映画の脚本の世界である。
今回のケースにおいて、この教諭が話を訊いた段階で現実に犯行をくいとめることができ
るのかどうか、またこの手の事件の本質はどこにあるのかなどについては、明日の 「こじ
ろう117」 で続きとして考えることにしたい。
「まさか?本当に」 ということを時々
しでかしては、飼い主を 「あぜん」 と
させることがある!? こじろう
(殺人未遂) 事件は、世間一般、特にその少女らと同年代の子をもつ親 (保護者) を
震撼させる衝撃的なものであったが、それに関する続報で、昨日興味深いニュースが地
元 (兵庫県) の某紙から配信された。
そのタイトルは 「長女の 『犯行予告』 聞いた教諭、受け流す」 というものであり、内
容は、
・・・・・宝塚市の放火事件で、殺人未遂などで兵庫県警に逮捕された市立中学校3年の
長女 (15才) と 同級生の少女 (14才) が級友に放火の予告をした際、同校教諭も
同席していたことが級友らの話でわかった。市教委によると教諭は 「『放火』 とか 『午前
2時』 いうことばは聞いておらず、家出でもするつもりかと思った」 と言い、その場で少女
らに 「あかんで」 と注意したという。
級友らによると長女は事件前日の8日、5時限目の授業に出席。一緒にいた少女と級友ら
に 「明日やる」 「午前2時に火をつける」 「親を刺す」 などと予告した。その際、授業を
していた教諭も話を聞いたが、 「まあまあ」 と受け流していたという。
(中略)
宝塚市教委は 「結果的に “サイン” を見逃した、と言われても仕方がない」 とコメント
している。・・・・・
というものである。
この記事を読んで、まず市教委のコメントは 「いかにも」 という感が否めないが、それは
ともかく、「なんだ。教師がハッキリと犯行予告?を聞いていたんじゃないか。なぜ止めな
かったんだ」 「教師の職務怠慢が招いた事件じゃないか」 などと非難・批判するのは簡
単である。しかしそういうことを言う人たちも、今回もし自分がその (教諭の) の立場に
いたとしたら、本当に真剣にその話を訊き、積極的に関与し、犯行を止めるところまでいき
ついたであろうかという疑問は大いにある。やはり後になって 「まさか?本当に実行する
とは思わなかった」 というのが本音となるのではないか。
決め手や前提になるのは、その日に至るまでのその長女の生活態度や言動などであるが、
仮に普段から 「いつそういう事件を起こしても不思議でない」 「いかにもそういう事件を
起こしそう」 という生徒だとしても、まさかまだ15才の少女が本当に自宅に放火し、まし
て真剣に親を殺そうとしているなどと “現実に” 予想し、事前に対処しろと言われても
それは難しいのではないか。一般の常識人 (少年少女を含む) であれば到底考えつ
かない、思いつかないことですらあるうえに、たとえ思いついたとしてもそれをイザ実行に
移すとなれば、これはもうドラマや映画の脚本の世界である。
今回のケースにおいて、この教諭が話を訊いた段階で現実に犯行をくいとめることができ
るのかどうか、またこの手の事件の本質はどこにあるのかなどについては、明日の 「こじ
ろう117」 で続きとして考えることにしたい。
「まさか?本当に」 ということを時々
しでかしては、飼い主を 「あぜん」 と
させることがある!? こじろう
2010年07月15日
“優先”? “専用”? それとも・・・(その3)
「こじろう117」・・・“優先”? “専用”? それとも・・・(その1) (その2) の続きである。
現行のいわゆる 「シルバーシート」 を “優先席” という 「あいまいな形」 でなく、
いっそのこと “専用席” としてしまった方が中途半端でなく、またいろいろと考える必
要がない分 “スッキリ” するのでは、という意見もあるようだが、それはそれでまたさ
まざまな支障も考えられる。
というのも、電車にしてもバスにしても、超過密あるいは過密状態にある時間帯は限ら
れており、たとえば車両の中の座席数と乗客数がほぼ同数、あるいはそれに近い場合、
“専用席” とされていることによって、空席が存在するにもかかわらず座る機会を奪うこ
とになってしまうからだ。
普段は特に座るつもりのない人、座る必要のない人であっても、体調が悪い、気分がす
ぐれないことはある。そのようなときに “専用席” しか空いていないとして、そこに腰を
下ろすことに抵抗を感じさせてしまうのは酷であるといえるだろう。
「あいまいさ」 はときに大きなトラブルの原因となることもあるが、「あいまいさ」 のおか
げ (この場合は “専用” とするのでなく “優先” とすること) で柔軟な対応をとれ
たり、物事を円滑に遂行させることにつながる場合もあるのだ。
昨日も述べたように、限られた数の座席を、その時誰が利用すべきかということは特別
に考えることではなく、人としての “社会的常識” をもって瞬時に判断できることであ
る。しかし世の中には、その “社会的常識” が備わっていない人が多く、あるいは備
わっているとしても、その程度に差があることを考慮すれば、やはり 「優先席」 あるい
はそれに類するものはどうしても必要になると結論づけざるをえないだろう。
また先述の “社会的常識” をどのようにして身につければよいかということでいえば、
これはやはりその人の人格が形成される時期に依存するところが大きいといえる。
となれば、やはり最大のポイントは特に幼少期の子どもに対して日頃、親 (保護者)
がどういう姿勢を示しているかということになる。一旦その基本的人格やものの考え方
が確立されてしまえば、それを修正することは不可能でなくても困難ではある。ことに
他人に対する思いやりとか接し方というのは、それを身に付ける過程における親 (保
護者) の影響力は相当に大きいものであるだろう。
「自分は (ダメな) 親を反面教師としてきた」 という人もたしかにいるが、そういう人
たちはどちらかといえば極めて少数派に属すると考えるべきである。やはり親 (保護
者) が自ら子どもに手本、見本を示しながら、「社会的常識」 をしっかりと教え込ん
でいくことがあらゆる問題を解決する 「根本の手立て」 であることに疑いはない。
「実際に支払うことができるのにもかかわらず、給食費を払わない親」 を見て育った
その子どもが、将来自分の子どもの給食費を払う可能性は極めて小さいのである。
( 「こじろう117」・・・赤信号、みんなで渡れば・・・参照)
飼い主を 「反面教師」 として日々
過ごしているつもりの!? こじろう
現行のいわゆる 「シルバーシート」 を “優先席” という 「あいまいな形」 でなく、
いっそのこと “専用席” としてしまった方が中途半端でなく、またいろいろと考える必
要がない分 “スッキリ” するのでは、という意見もあるようだが、それはそれでまたさ
まざまな支障も考えられる。
というのも、電車にしてもバスにしても、超過密あるいは過密状態にある時間帯は限ら
れており、たとえば車両の中の座席数と乗客数がほぼ同数、あるいはそれに近い場合、
“専用席” とされていることによって、空席が存在するにもかかわらず座る機会を奪うこ
とになってしまうからだ。
普段は特に座るつもりのない人、座る必要のない人であっても、体調が悪い、気分がす
ぐれないことはある。そのようなときに “専用席” しか空いていないとして、そこに腰を
下ろすことに抵抗を感じさせてしまうのは酷であるといえるだろう。
「あいまいさ」 はときに大きなトラブルの原因となることもあるが、「あいまいさ」 のおか
げ (この場合は “専用” とするのでなく “優先” とすること) で柔軟な対応をとれ
たり、物事を円滑に遂行させることにつながる場合もあるのだ。
昨日も述べたように、限られた数の座席を、その時誰が利用すべきかということは特別
に考えることではなく、人としての “社会的常識” をもって瞬時に判断できることであ
る。しかし世の中には、その “社会的常識” が備わっていない人が多く、あるいは備
わっているとしても、その程度に差があることを考慮すれば、やはり 「優先席」 あるい
はそれに類するものはどうしても必要になると結論づけざるをえないだろう。
また先述の “社会的常識” をどのようにして身につければよいかということでいえば、
これはやはりその人の人格が形成される時期に依存するところが大きいといえる。
となれば、やはり最大のポイントは特に幼少期の子どもに対して日頃、親 (保護者)
がどういう姿勢を示しているかということになる。一旦その基本的人格やものの考え方
が確立されてしまえば、それを修正することは不可能でなくても困難ではある。ことに
他人に対する思いやりとか接し方というのは、それを身に付ける過程における親 (保
護者) の影響力は相当に大きいものであるだろう。
「自分は (ダメな) 親を反面教師としてきた」 という人もたしかにいるが、そういう人
たちはどちらかといえば極めて少数派に属すると考えるべきである。やはり親 (保護
者) が自ら子どもに手本、見本を示しながら、「社会的常識」 をしっかりと教え込ん
でいくことがあらゆる問題を解決する 「根本の手立て」 であることに疑いはない。
「実際に支払うことができるのにもかかわらず、給食費を払わない親」 を見て育った
その子どもが、将来自分の子どもの給食費を払う可能性は極めて小さいのである。
( 「こじろう117」・・・赤信号、みんなで渡れば・・・参照)
飼い主を 「反面教師」 として日々
過ごしているつもりの!? こじろう
2010年07月14日
“優先”? “専用”? それとも・・・(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・“優先”? “専用”? それとも・・・(その1) の続きである。
最近、自分自身が公共交通機関を利用することはほとんどないため、いわゆる 「シルバ
ーシート (優先席)」 の実態を自らの目で把握しているわけではなく、勝手で無責任な
ことはいえないという自覚はある。また大都市圏と地方都市においては大きく実情も異な
るだろうし、さらに言えば電車とバスでもたとえばその車内環境や乗客の出入りの頻度な
どはやはり違うため、この件に関して一概に論ずることには所詮無理があることを前提と
すべきでもある。しかしそうはいっても、その根底にあるもの、根本的な部分については
やはり共通点はあるといわざるをえない。
もともと 「シルバーシート」 とは、その名の通り 「シルバー」 つまり 「お年寄り」 の
ための優先席としてスタートしたものだが、1990年代の後半くらいからはその利用対象
者をケガをしている人、妊娠中の女性のほか、ハンディキャップをもった人々に拡大する
ため、その呼称も 「シルバーシート」 から 「優先席」 「優先座席」 「思いやり席」 な
どへの変更が進んできているようである。また大都市圏の一部の鉄道では 「 “全座席”
を優先座席とする」 という方針が打ち出され、「特定の優先席」 はすでに廃止されてい
るという。
「優先席」 というのは、それを必要とする人たちを 「優先」 すなわちその必要のある
ときにその人たちに席を 「ゆずる」 という考え方が前提になっているが、そもそもその
考え方自体に 「~しなくてはならない」 という “義務的” ないしは “強制的” な
意味合いを含んでいることは否定できないであろう。しかし本来、こういうことは義務や
命令で行われることでなく、人として “当然”、“自然”、あるいは “あたりまえ” に
なされるべき行為である。
そういう観点でいえば、「 “全座席” を優先座席」 としている先の鉄道会社の方針は
何も特筆すべきものでもなく、ごくごく普通のものといういい方ができるのであり、またこ
の件についての検討もこれ以上必要がないということになる。
しかし、現実には日常のあらゆることに関して、その成り行きにまかせたときには 「本来
あるべき姿やかたち」 にならない方が多いのが普通である。法や規則、ルールを整備する
必要性があるのはそのためといういい方もできるだろう。現実にはこの 「優先席」 という
ようなものが存在しなくてはならない背景や理由があるわけで、それではその 「優先席」
あるいは 「専用席」 のあり方、とらえ方をどう考えるべきかということについては、この
続きとして明日の 「こじろう117」 で述べることにしたいと思う。
飼い主宅の一室を、勝手に自らの
「専用室」 として占有している
!? こじろう
最近、自分自身が公共交通機関を利用することはほとんどないため、いわゆる 「シルバ
ーシート (優先席)」 の実態を自らの目で把握しているわけではなく、勝手で無責任な
ことはいえないという自覚はある。また大都市圏と地方都市においては大きく実情も異な
るだろうし、さらに言えば電車とバスでもたとえばその車内環境や乗客の出入りの頻度な
どはやはり違うため、この件に関して一概に論ずることには所詮無理があることを前提と
すべきでもある。しかしそうはいっても、その根底にあるもの、根本的な部分については
やはり共通点はあるといわざるをえない。
もともと 「シルバーシート」 とは、その名の通り 「シルバー」 つまり 「お年寄り」 の
ための優先席としてスタートしたものだが、1990年代の後半くらいからはその利用対象
者をケガをしている人、妊娠中の女性のほか、ハンディキャップをもった人々に拡大する
ため、その呼称も 「シルバーシート」 から 「優先席」 「優先座席」 「思いやり席」 な
どへの変更が進んできているようである。また大都市圏の一部の鉄道では 「 “全座席”
を優先座席とする」 という方針が打ち出され、「特定の優先席」 はすでに廃止されてい
るという。
「優先席」 というのは、それを必要とする人たちを 「優先」 すなわちその必要のある
ときにその人たちに席を 「ゆずる」 という考え方が前提になっているが、そもそもその
考え方自体に 「~しなくてはならない」 という “義務的” ないしは “強制的” な
意味合いを含んでいることは否定できないであろう。しかし本来、こういうことは義務や
命令で行われることでなく、人として “当然”、“自然”、あるいは “あたりまえ” に
なされるべき行為である。
そういう観点でいえば、「 “全座席” を優先座席」 としている先の鉄道会社の方針は
何も特筆すべきものでもなく、ごくごく普通のものといういい方ができるのであり、またこ
の件についての検討もこれ以上必要がないということになる。
しかし、現実には日常のあらゆることに関して、その成り行きにまかせたときには 「本来
あるべき姿やかたち」 にならない方が多いのが普通である。法や規則、ルールを整備する
必要性があるのはそのためといういい方もできるだろう。現実にはこの 「優先席」 という
ようなものが存在しなくてはならない背景や理由があるわけで、それではその 「優先席」
あるいは 「専用席」 のあり方、とらえ方をどう考えるべきかということについては、この
続きとして明日の 「こじろう117」 で述べることにしたいと思う。
飼い主宅の一室を、勝手に自らの
「専用室」 として占有している
!? こじろう
2010年07月13日
“優先”? “専用”? それとも・・・(その1)
去る9日、某紙社会面に、一瞬自らの目を疑うような記事を見つけた。そのタイトルは
「60歳女性、男子高校生に重傷を負わせる」 というものであるが、“自分の目を疑う”
というのは 「“60歳女性” と “男子高校生” 、つまり今回の加害者と被害者が
逆ではないか」 と思ったからである。一応もう一度見直してみても、やはり加害者は
“60歳女性” の方だったが、これを 「近頃は60歳の女性といってもなかなか・・・
などとして片付けてしまうのはあまりに安易では」 と、その続きを読んで考えさせられ
たのである。
その記事 (事件) の内容は、
・・・長崎県内の路線バス車内でシルバーシートに座っていた男子高校生の顔を傘で突く
などして重傷を負わせたということで、8日、長崎県警は60歳の女性容疑者を逮捕した。
女性が 「学生のくせになんで (シルバーシートに) 座っているのか」 などと言いがか
りをつけて高校生を傘で殴り、鼻の骨を折るなどのケガをさせた・・・
というものである。
このニュースの続報や詳報をその後目にしていないので、この簡単な記事の内容をもって
事件そのものについてあれこれと言及するには限界があるが、あくまでも推測として、た
とえば最初はこの女性が “それとなく注意した” 程度のことに男子高校生がいわゆる
「逆ギレ」 して暴言を吐き、それに対して女性がつい?手 (傘) を出してしまったなど
の可能性も考えられる。
しかしいずれにせよ、“傘という凶器” を用いて一方的に?、しかも顔面にケガを負わせ
たという事実は絶対に見過ごすことのできないものである。「鼻の骨が折れる」 ということ
がどれほどの苦痛を伴うのかは見当もつかないし、また想像したくもない。だがそれにと
どまらず、もしそのすぐ上の眼球でも傷つけていたとしたら、それはその高校生の将来に
わたり取り返しのつかないことになる可能性も出てくるだろう。したがっていかなる理由
があろうとも、今回の “暴行” 自体は決して容認されるものではないことはいうまでも
ない。
しかしそれはその通りとして、今回の事件が起きた明らかな原因の一つである 「シルバ
ーシート」 のあり方について、(事件そのものとは別に) 考えてみるのもいい機会で
あるかもしれない。そのあたりについては明日の 「こじろう117」 でこの続きとして
触れてみたいと思う。
ときどき飼い主が自らの目を疑うよう
なことをしでかす!? こじろう
「60歳女性、男子高校生に重傷を負わせる」 というものであるが、“自分の目を疑う”
というのは 「“60歳女性” と “男子高校生” 、つまり今回の加害者と被害者が
逆ではないか」 と思ったからである。一応もう一度見直してみても、やはり加害者は
“60歳女性” の方だったが、これを 「近頃は60歳の女性といってもなかなか・・・
などとして片付けてしまうのはあまりに安易では」 と、その続きを読んで考えさせられ
たのである。
その記事 (事件) の内容は、
・・・長崎県内の路線バス車内でシルバーシートに座っていた男子高校生の顔を傘で突く
などして重傷を負わせたということで、8日、長崎県警は60歳の女性容疑者を逮捕した。
女性が 「学生のくせになんで (シルバーシートに) 座っているのか」 などと言いがか
りをつけて高校生を傘で殴り、鼻の骨を折るなどのケガをさせた・・・
というものである。
このニュースの続報や詳報をその後目にしていないので、この簡単な記事の内容をもって
事件そのものについてあれこれと言及するには限界があるが、あくまでも推測として、た
とえば最初はこの女性が “それとなく注意した” 程度のことに男子高校生がいわゆる
「逆ギレ」 して暴言を吐き、それに対して女性がつい?手 (傘) を出してしまったなど
の可能性も考えられる。
しかしいずれにせよ、“傘という凶器” を用いて一方的に?、しかも顔面にケガを負わせ
たという事実は絶対に見過ごすことのできないものである。「鼻の骨が折れる」 ということ
がどれほどの苦痛を伴うのかは見当もつかないし、また想像したくもない。だがそれにと
どまらず、もしそのすぐ上の眼球でも傷つけていたとしたら、それはその高校生の将来に
わたり取り返しのつかないことになる可能性も出てくるだろう。したがっていかなる理由
があろうとも、今回の “暴行” 自体は決して容認されるものではないことはいうまでも
ない。
しかしそれはその通りとして、今回の事件が起きた明らかな原因の一つである 「シルバ
ーシート」 のあり方について、(事件そのものとは別に) 考えてみるのもいい機会で
あるかもしれない。そのあたりについては明日の 「こじろう117」 でこの続きとして
触れてみたいと思う。
ときどき飼い主が自らの目を疑うよう
なことをしでかす!? こじろう
2010年07月12日
“不気味!” 目的は何だ???
11日のS紙朝刊に 「受験者へ不審勧誘」・・・「1000円で結果通知」 というタイトルの
小さな記事が載っていた。
その概要は、
・・・10日に始まった県内公立学校教員採用1次試験の会場周辺で、スーツやネクタイ姿
の男性らから 「試験結果の発表直後に個別に結果を知らせる」 などと言われ、手数料と
して1000円を支払っていた受験者が相次いでいたことが分かった。県教委が把握しただ
けでも、支払った人数は計115人に上るという。男性らは同日午前、会場に向かう受験者
に氏名、住所、受験番号、電話番号などを記入する申込用紙と筆記用具を会場敷地外で
手渡していたということで、県教委が関与していると誤解した受験生もいたようだ。一次試
験の結果は8月6日に受験者に郵便で発送すると同時に、午後1時、県教委のホームペ
ージに掲載されることになっている・・・
というものである。
この記事を読んでまずある種の 「懐かしさ」 をおぼえるとしたら、それはどのくらいの年代
以上であろうか。我々の大学等受験期には、今のように受験先の方から (郵便等で) 結果
を知らせてくれることはまず考えられず、またインターネットなどもちろん普及していなかった
ので、試験の合否は発表日に受験先の掲示板で確認するしか方法はなかった。しかし、受
験先が遠隔地などの場合はその都度確認に出向けないため、そこに登場したのが 「受験時
に所定の手数料 (自分の時代には500円が相場だったと思うが) を支払い、結果を電話
や電報などで知らせてくれるというサービス?」 であるが、実際にはしっかりした組織では
なく、学生などが小遣い稼ぎに個人的に行なっているものが一般的だったようである。自分
自身は見ず知らずの他人から大事な結果を知らされるのは好まなかったため、面倒でも自
らの足で見にいくことにしたが、友人の中にはお金を支払っただけで結局何も連絡をもらえ
ない、つまりまんまと騙されてしまった人も現実に存在したおぼえがある。
今回の件は大学等の試験とは違うが、もともと郵便で正式な通知が届くことが前提となって
いるうえに、ホームページでも確認できるのである。しかも昔の世間知らず?の田舎受験生
とは異なり、現在の情報社会の最先端にいるハズの (わかっているだけで115人もの)
若者が、「なぜ、支払う必要のないお金を支払ってしまったのか」 は素朴な疑問である。
また、ある意味それ以上に “不気味” なのが、その男性らの 「真の目的」 である。結果
として120名近くの受験生から1000円を集めることができたとはいえ、総額にしてせいぜ
い10~15万円程度の売上げ?である。ネットや電話におけるものでなく、実際に 「顔を
晒して」 まで不審勧誘するだけのリスクに見合う 「もうけ」 になるとは、どうしても思え
ないのだ。
今回の 「勧誘」 が不審なものだとして、それが金銭的な問題で済むのならまだよいが、
提供した個人情報が何か別のことに利用、悪用されるのではという心配は尽きない。そう
ならないことを願うとともに、「簡単にさまざまな呼びかけに応じてしまうことの危険性」 を
世代を問わず周知させる必要性を強く感ずるものである。
見知らぬ人からオヤツをもらう
ことの危険性をよく理解して
いるつもりの!? こじろう
小さな記事が載っていた。
その概要は、
・・・10日に始まった県内公立学校教員採用1次試験の会場周辺で、スーツやネクタイ姿
の男性らから 「試験結果の発表直後に個別に結果を知らせる」 などと言われ、手数料と
して1000円を支払っていた受験者が相次いでいたことが分かった。県教委が把握しただ
けでも、支払った人数は計115人に上るという。男性らは同日午前、会場に向かう受験者
に氏名、住所、受験番号、電話番号などを記入する申込用紙と筆記用具を会場敷地外で
手渡していたということで、県教委が関与していると誤解した受験生もいたようだ。一次試
験の結果は8月6日に受験者に郵便で発送すると同時に、午後1時、県教委のホームペ
ージに掲載されることになっている・・・
というものである。
この記事を読んでまずある種の 「懐かしさ」 をおぼえるとしたら、それはどのくらいの年代
以上であろうか。我々の大学等受験期には、今のように受験先の方から (郵便等で) 結果
を知らせてくれることはまず考えられず、またインターネットなどもちろん普及していなかった
ので、試験の合否は発表日に受験先の掲示板で確認するしか方法はなかった。しかし、受
験先が遠隔地などの場合はその都度確認に出向けないため、そこに登場したのが 「受験時
に所定の手数料 (自分の時代には500円が相場だったと思うが) を支払い、結果を電話
や電報などで知らせてくれるというサービス?」 であるが、実際にはしっかりした組織では
なく、学生などが小遣い稼ぎに個人的に行なっているものが一般的だったようである。自分
自身は見ず知らずの他人から大事な結果を知らされるのは好まなかったため、面倒でも自
らの足で見にいくことにしたが、友人の中にはお金を支払っただけで結局何も連絡をもらえ
ない、つまりまんまと騙されてしまった人も現実に存在したおぼえがある。
今回の件は大学等の試験とは違うが、もともと郵便で正式な通知が届くことが前提となって
いるうえに、ホームページでも確認できるのである。しかも昔の世間知らず?の田舎受験生
とは異なり、現在の情報社会の最先端にいるハズの (わかっているだけで115人もの)
若者が、「なぜ、支払う必要のないお金を支払ってしまったのか」 は素朴な疑問である。
また、ある意味それ以上に “不気味” なのが、その男性らの 「真の目的」 である。結果
として120名近くの受験生から1000円を集めることができたとはいえ、総額にしてせいぜ
い10~15万円程度の売上げ?である。ネットや電話におけるものでなく、実際に 「顔を
晒して」 まで不審勧誘するだけのリスクに見合う 「もうけ」 になるとは、どうしても思え
ないのだ。
今回の 「勧誘」 が不審なものだとして、それが金銭的な問題で済むのならまだよいが、
提供した個人情報が何か別のことに利用、悪用されるのではという心配は尽きない。そう
ならないことを願うとともに、「簡単にさまざまな呼びかけに応じてしまうことの危険性」 を
世代を問わず周知させる必要性を強く感ずるものである。
見知らぬ人からオヤツをもらう
ことの危険性をよく理解して
いるつもりの!? こじろう
2010年07月11日
『見かけで判断』 は禁物!!!(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・『見かけで判断』 は禁物!!!(その1)・・・の続きである。
「人は見かけによらない」 というのは、裏を返せば 「人はある程度まで見かけで決まる」
と解釈できる。しかしそうはいっても、その人の “見かけ” や “第一印象” 、さらにいえ
ば “最初 (当初) 抱いたイメージ” などを 「信じこんでしまう」 ことにより気がついた
ら人間関係上の大変な重荷を背負ったり、悩みを抱えてしまうということは誰にでも日常
ありうることではないだろうか。
雑誌やネット上の 「悩み相談」 のようなものを目にすることがときどきある。その中で
比較的目立つのが、小さなこどもがいる母親同士 (「ママ友」? というのだろうか) の
関係で他人にいえないような悩みを抱えている、というものである。
その代表的パターンとしては、
・・・初めて出会い、話をしたときの印象から 「この人となら仲良くなれそう。お互いになん
でも相談し合えたり協力し合えたりする気がする」 と思って徐々に親密になっていく。しか
しその当初は何も問題なくむしろ本当にいい人と知り合えたと思っていたところ、次第に慣
れ合いになり、相手の “気安さ” や、場合によっては “図々しさ” などが垣間見えてく
ると疎ましく思えてしまうようになる。あるいは、あまりにいろいろと親切にされすぎて恐縮
してしまい、時には自分の家庭のことまで干渉されがちになると、その関係を重荷に感じ
るようになる。さりとて日常こどもに関する接触は必要なため、簡単にその関係をたち切る
わけにもいかず、また一度属した “グループ” から抜け出すのも難しい。
そういう時こそ頼りになるハズ?のダンナなどに相談しても 「オマエの (最初の) 他人
に対する見抜きが甘いからそういうことになるんだ」 などと一方的に責められるばかりで、
「そんなこと言ったって最初からそんなことわかるわけないでしょ」 などと余計な夫婦ケン
カにさえ発展しかねない・・・
というようなものである。
たしかに最初の “見かけ” や “第一印象” のよさというのは極めて大切であるし、人間
同士のほとんどはそこから始まるわけであるが、実際にはある程度の年月を経てみないと
人や物事の本質はわからないのがまた普通であり、ここは 「こうすべきである」 などと
いう解答がないのはあたりまえであろう。先のことを考えるにしても、キリがないのである。
いずれにせよ無難なのは、最初 (当初) 抱いたイメージを 「安易に信じ込むことはしない」
ということ、また特定の関係に 「のめり込まない」 「必要以上に深入りしない」 ためにも、
(相手になるべく悟られないように) 一定の (目に見えない) 距離をおいて接するように
心がける、ということなのだろうか。
もっとも他人のことについては客観的にいろいろいうことができても、イザ自分のこととなる
と理想的には運ばないものこそが 「人間関係」 というものであり、数学の問題を解くよう
なわけにはいかないのもまた事実である。
飼い主にはいえない悩みをいろいろ
抱えているらしく、ときどき意味不明
な行動をとる!? こじろう
「人は見かけによらない」 というのは、裏を返せば 「人はある程度まで見かけで決まる」
と解釈できる。しかしそうはいっても、その人の “見かけ” や “第一印象” 、さらにいえ
ば “最初 (当初) 抱いたイメージ” などを 「信じこんでしまう」 ことにより気がついた
ら人間関係上の大変な重荷を背負ったり、悩みを抱えてしまうということは誰にでも日常
ありうることではないだろうか。
雑誌やネット上の 「悩み相談」 のようなものを目にすることがときどきある。その中で
比較的目立つのが、小さなこどもがいる母親同士 (「ママ友」? というのだろうか) の
関係で他人にいえないような悩みを抱えている、というものである。
その代表的パターンとしては、
・・・初めて出会い、話をしたときの印象から 「この人となら仲良くなれそう。お互いになん
でも相談し合えたり協力し合えたりする気がする」 と思って徐々に親密になっていく。しか
しその当初は何も問題なくむしろ本当にいい人と知り合えたと思っていたところ、次第に慣
れ合いになり、相手の “気安さ” や、場合によっては “図々しさ” などが垣間見えてく
ると疎ましく思えてしまうようになる。あるいは、あまりにいろいろと親切にされすぎて恐縮
してしまい、時には自分の家庭のことまで干渉されがちになると、その関係を重荷に感じ
るようになる。さりとて日常こどもに関する接触は必要なため、簡単にその関係をたち切る
わけにもいかず、また一度属した “グループ” から抜け出すのも難しい。
そういう時こそ頼りになるハズ?のダンナなどに相談しても 「オマエの (最初の) 他人
に対する見抜きが甘いからそういうことになるんだ」 などと一方的に責められるばかりで、
「そんなこと言ったって最初からそんなことわかるわけないでしょ」 などと余計な夫婦ケン
カにさえ発展しかねない・・・
というようなものである。
たしかに最初の “見かけ” や “第一印象” のよさというのは極めて大切であるし、人間
同士のほとんどはそこから始まるわけであるが、実際にはある程度の年月を経てみないと
人や物事の本質はわからないのがまた普通であり、ここは 「こうすべきである」 などと
いう解答がないのはあたりまえであろう。先のことを考えるにしても、キリがないのである。
いずれにせよ無難なのは、最初 (当初) 抱いたイメージを 「安易に信じ込むことはしない」
ということ、また特定の関係に 「のめり込まない」 「必要以上に深入りしない」 ためにも、
(相手になるべく悟られないように) 一定の (目に見えない) 距離をおいて接するように
心がける、ということなのだろうか。
もっとも他人のことについては客観的にいろいろいうことができても、イザ自分のこととなる
と理想的には運ばないものこそが 「人間関係」 というものであり、数学の問題を解くよう
なわけにはいかないのもまた事実である。
飼い主にはいえない悩みをいろいろ
抱えているらしく、ときどき意味不明
な行動をとる!? こじろう
2010年07月10日
『見かけで判断』 は禁物!!!(その1)
9日の某紙朝刊に 「暴力団組長 警官に暴力」 というような見出しの小さな記事があり、
思わず目を奪われてしまった。その瞬間、もう35年ほど前になるだろうか、梅宮辰夫らが
出演した 「県警 対 組織暴力」 というタイトルの映画で、警官を相手に暴力団組員が
暴れるシーンを思い出し、「イマドキの暴力団にもそんな (警官相手に暴行するほどの)
度胸?があるのか」 と驚いてしまったが、よく読んでみるとなんということはない、「(その
組とは関係のない件で路上に駐車していた) 黒塗りの警察車両を別の組 (暴力団) の
車と勘違いした組長らが、 『お前らどこの (組の) もんじゃい』 と怒鳴ってドアを蹴った
り、乗っていた私服姿の巡査部長の肩をつかんで引きずり降ろそうとした」 だけのことで
あり、実態を知った途端に (まことに不謹慎ながら) 正直ガッカリ?してしまったという
次第である。
この事件、「まぬけな話だ」 といえばそれで終わりであるが、よくよく考えてみると、今回
被害に遭った?その警察車両、“黒塗りのセダンタイプ” という 「いかにもそれらしい」
ものであり、またよくTVのニュースなどで目にする、暴力団事務所の一斉捜索等に向かう
私服の警察関係者らの風貌や雰囲気は、「一体どちらが “その筋の人間” なのか」 とい
う区別がつかないほどであるため、まさに 「見かけ」 だけでいえば警察関係者も暴力団
員も (同業者同士ですら) 判別不能であるのが普通ということだろう。
われわれ一般人?の日常の中でも、今回のことを笑って済ますことのできないような場面
は決して少なくない。特に一瞬の間違いではないが、最初に抱いたイメージや印象がその
後大きく異なる、つまり見込み違いにより、時にとんでもない事態に進展してしまうこともあ
るわけで、そのあたりのことは明日の 「こじろう117」 で続きを述べたいと思う。
見かけによらず? 「凶暴」 な面を
特に飼い主に対して日常見せることが
よくある!? こじろう
思わず目を奪われてしまった。その瞬間、もう35年ほど前になるだろうか、梅宮辰夫らが
出演した 「県警 対 組織暴力」 というタイトルの映画で、警官を相手に暴力団組員が
暴れるシーンを思い出し、「イマドキの暴力団にもそんな (警官相手に暴行するほどの)
度胸?があるのか」 と驚いてしまったが、よく読んでみるとなんということはない、「(その
組とは関係のない件で路上に駐車していた) 黒塗りの警察車両を別の組 (暴力団) の
車と勘違いした組長らが、 『お前らどこの (組の) もんじゃい』 と怒鳴ってドアを蹴った
り、乗っていた私服姿の巡査部長の肩をつかんで引きずり降ろそうとした」 だけのことで
あり、実態を知った途端に (まことに不謹慎ながら) 正直ガッカリ?してしまったという
次第である。
この事件、「まぬけな話だ」 といえばそれで終わりであるが、よくよく考えてみると、今回
被害に遭った?その警察車両、“黒塗りのセダンタイプ” という 「いかにもそれらしい」
ものであり、またよくTVのニュースなどで目にする、暴力団事務所の一斉捜索等に向かう
私服の警察関係者らの風貌や雰囲気は、「一体どちらが “その筋の人間” なのか」 とい
う区別がつかないほどであるため、まさに 「見かけ」 だけでいえば警察関係者も暴力団
員も (同業者同士ですら) 判別不能であるのが普通ということだろう。
われわれ一般人?の日常の中でも、今回のことを笑って済ますことのできないような場面
は決して少なくない。特に一瞬の間違いではないが、最初に抱いたイメージや印象がその
後大きく異なる、つまり見込み違いにより、時にとんでもない事態に進展してしまうこともあ
るわけで、そのあたりのことは明日の 「こじろう117」 で続きを述べたいと思う。
見かけによらず? 「凶暴」 な面を
特に飼い主に対して日常見せることが
よくある!? こじろう
2010年07月09日
『常識レベル』 がわかってしまう一言???(その3)
『常識レベル』 がわかってしまう一言???(その1) および (その2) の続きである。
今日は昨日までの 「何気ない一言」 というのとは少々異なるが、やはり 「その人の社会
的 『常識レベル』 が知れてしまうと思われること」 に関しての話である。
単に年齢が上であるという理由でやたら “先輩風” を吹かせる、特に中高年の男性をたま
に見かけることがある。言葉遣いもそうであるし相手の呼び方も 「△△ “君”」を多用し、
ヒドイ時には呼び捨てにすることすらあるのだ。学生時代ならもちろん社会においても、“同
一組織内” における 「上司と部下」 あるいは 「先輩と後輩」 の関係では基本的に違
和感はないが、ここで取り上げるのは、「もともとそういう関係ではない」 または 「以前は
そういう関係にあったが今はそうではない」 ケースについてである。
たとえば取引先企業の担当者同士の関係では、たとえ年齢・肩書・キャリアの差がある (一
方がA社の課長で40才、他方がB社の3年目社員で25才のような場合) 、また取引先企業
同士の “力関係” の差があるケースでも、そこでは他組織の “一社会人同士としての立場”
が尊重されるべきで、「△△ “君” 」 という呼び方、ましてや呼び捨てなどは本来許されな
いのが実社会の常識である。しかしそのあたりのことがわかっていない、あるいはどうも勘違
いしているのではという中高年男性はそれなりにいるようである。
さらに、学生時代の先輩・後輩、または同期であった場合、同窓会や仲間内の集まりで当時の
思い出を振り返るような場面は別として、それ以外のとき、たとえばたまたま他組織同士で業
務上のつながりができたような場合は、やはりけじめとしてお互いに敬称を用いるのは当然で
ある。ましてそのような従前の関係が全くないにもかかわらず、単に年下だからといって 「△
△ “君” 」 などと呼ぶようなことをすれば、その人の社会的 「常識レベル」 はかなり劣っ
たものと推測されるであろう。かつては 「師弟」 の関係にあったとしても、その教え子が立
派な社会人になったからには、当然敬称を用いるのが常識のある師匠 (教師) というもの
である。
現政権党の最高顧問の一人で衆院副議長まで務めたW部衆院議員 (78才)。今や 「ご意
見番」 的立場として、歯に衣着せぬ言動は聞いていて時に小気味よく感ずることもあるが、
いくら自分より年齢や議員としてのキャリア等が低いからといって、現職の総理大臣や党幹事
長(いずれも当時) をつかまえて (直接目の前でなくとも) 「鳩山 “君” が」 とか 「小沢
“君” が」 などといっているのを耳にすると、申し訳ないが政治家としての実績はともかく、
社会人としての 「基本的常識レベル」 は決して高くない、あるいはいかにも 「旧来型の政
治家 “先生” らしいなあ」 と感じざるを得ないのである。
犬としてはすでに 「成人」 している
年齢なのに、相変わらず飼い主からは
「こども扱い」 されることに不満の
ある!? こじろう
今日は昨日までの 「何気ない一言」 というのとは少々異なるが、やはり 「その人の社会
的 『常識レベル』 が知れてしまうと思われること」 に関しての話である。
単に年齢が上であるという理由でやたら “先輩風” を吹かせる、特に中高年の男性をたま
に見かけることがある。言葉遣いもそうであるし相手の呼び方も 「△△ “君”」を多用し、
ヒドイ時には呼び捨てにすることすらあるのだ。学生時代ならもちろん社会においても、“同
一組織内” における 「上司と部下」 あるいは 「先輩と後輩」 の関係では基本的に違
和感はないが、ここで取り上げるのは、「もともとそういう関係ではない」 または 「以前は
そういう関係にあったが今はそうではない」 ケースについてである。
たとえば取引先企業の担当者同士の関係では、たとえ年齢・肩書・キャリアの差がある (一
方がA社の課長で40才、他方がB社の3年目社員で25才のような場合) 、また取引先企業
同士の “力関係” の差があるケースでも、そこでは他組織の “一社会人同士としての立場”
が尊重されるべきで、「△△ “君” 」 という呼び方、ましてや呼び捨てなどは本来許されな
いのが実社会の常識である。しかしそのあたりのことがわかっていない、あるいはどうも勘違
いしているのではという中高年男性はそれなりにいるようである。
さらに、学生時代の先輩・後輩、または同期であった場合、同窓会や仲間内の集まりで当時の
思い出を振り返るような場面は別として、それ以外のとき、たとえばたまたま他組織同士で業
務上のつながりができたような場合は、やはりけじめとしてお互いに敬称を用いるのは当然で
ある。ましてそのような従前の関係が全くないにもかかわらず、単に年下だからといって 「△
△ “君” 」 などと呼ぶようなことをすれば、その人の社会的 「常識レベル」 はかなり劣っ
たものと推測されるであろう。かつては 「師弟」 の関係にあったとしても、その教え子が立
派な社会人になったからには、当然敬称を用いるのが常識のある師匠 (教師) というもの
である。
現政権党の最高顧問の一人で衆院副議長まで務めたW部衆院議員 (78才)。今や 「ご意
見番」 的立場として、歯に衣着せぬ言動は聞いていて時に小気味よく感ずることもあるが、
いくら自分より年齢や議員としてのキャリア等が低いからといって、現職の総理大臣や党幹事
長(いずれも当時) をつかまえて (直接目の前でなくとも) 「鳩山 “君” が」 とか 「小沢
“君” が」 などといっているのを耳にすると、申し訳ないが政治家としての実績はともかく、
社会人としての 「基本的常識レベル」 は決して高くない、あるいはいかにも 「旧来型の政
治家 “先生” らしいなあ」 と感じざるを得ないのである。
犬としてはすでに 「成人」 している
年齢なのに、相変わらず飼い主からは
「こども扱い」 されることに不満の
ある!? こじろう
2010年07月08日
『常識レベル』 がわかってしまう一言???(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・『常識レベル』 がわかってしまう一言???(その1) の
続きである。
それなりの地位や立場にあり、立派そうな身なりに包まれて “紳士・淑女” 然として
いるにもかかわらず、その口から発せられる何気ない 「一言」 「ことば遣い」 「言い
方」 により、思いがけず社会的な 「常識レベル」 の低さが露呈してしまっている人
をよく見かける気がする。
先日ちょっとした打合せのために某ファミレスでお茶を飲む機会があったが、自分たちの
近くのテーブルで食事をしていた、服装や雰囲気もそれなりに立派でしっかりした感じの
中年の男性がその店のスタッフの方に向かって 「オイ、水だ」 とグラスを掲げている姿
を目にしてしまったのである。それはいかにも 「こちらは客なんだぞ」 という雰囲気を
醸しだしているものであった。このような場合 (本来は失礼なしぐさとはいえ) 手招き
することは仕方ないとしても、そのスタッフがテーブルまでやってきた際に 「すみません
が、水をお願いします」 といえば、周囲が抱く印象も 「この男性は見かけどおり紳士だ
なあ」 ということになるのだろうに、ほんの一つの言動でイメージががらりと変わってし
まうのは他人事とはいえ非常に残念なことである。またせまい世間のこと、この男性を知
っていてそれまで尊敬のまなざしで見ていた人がその場に居合わせていないとも限らな
いのである。
飲食店などでは、(アルコールが入っているいないにかかわらず、また “高級な店” “大
衆的な店” を問わず) サービスの提供を受ける側、つまり客側であったとしてもその
都度 「ありがとう」 とか 「すみませんね」 などということばを添えるのが真の紳士
・淑女というものである。もちろん店のスタッフの対応に全く誠意がみられないとか、明ら
かに立腹させられるようなことがあれば話は別であるが、「なぜ客の側が “ありがとう”
などという必要があるのだ」 とか 「金を払っているのはこっちなんだ」 ということを
口に出さずともそういう雰囲気を感じさせるだけで、「品性のない、かわいそうな人だな
あ」 と周囲は感じてしまうものなのだ。
ファストフード店などでたとえマニュアル通りの対応をしているアルバイトのスタッフであ
っても、やはり心は十分に伝わるものである。客側の方で 「気持のよい対応をしてくれ
てありがとう」 という趣旨の一言や雰囲気を出せば、サービスを提供する側としても逆
に 「ありがとうございますという気持ちで応じたい」 となるのは普通であり、結果的に、
「より気持ちのよいサービスを受けられる恩恵に与れる」 というものではないだろうか。
以下、やはりその当人は気づいていないが、社会人としての 「常識レベル」 を知られ
てしまうような例については明日の 「こじろう117」 でこの続きとして述べることにし
たいと思う。
飼い主の何気ない一言で、時にはひどく
落ち込むことのある!? こじろう
続きである。
それなりの地位や立場にあり、立派そうな身なりに包まれて “紳士・淑女” 然として
いるにもかかわらず、その口から発せられる何気ない 「一言」 「ことば遣い」 「言い
方」 により、思いがけず社会的な 「常識レベル」 の低さが露呈してしまっている人
をよく見かける気がする。
先日ちょっとした打合せのために某ファミレスでお茶を飲む機会があったが、自分たちの
近くのテーブルで食事をしていた、服装や雰囲気もそれなりに立派でしっかりした感じの
中年の男性がその店のスタッフの方に向かって 「オイ、水だ」 とグラスを掲げている姿
を目にしてしまったのである。それはいかにも 「こちらは客なんだぞ」 という雰囲気を
醸しだしているものであった。このような場合 (本来は失礼なしぐさとはいえ) 手招き
することは仕方ないとしても、そのスタッフがテーブルまでやってきた際に 「すみません
が、水をお願いします」 といえば、周囲が抱く印象も 「この男性は見かけどおり紳士だ
なあ」 ということになるのだろうに、ほんの一つの言動でイメージががらりと変わってし
まうのは他人事とはいえ非常に残念なことである。またせまい世間のこと、この男性を知
っていてそれまで尊敬のまなざしで見ていた人がその場に居合わせていないとも限らな
いのである。
飲食店などでは、(アルコールが入っているいないにかかわらず、また “高級な店” “大
衆的な店” を問わず) サービスの提供を受ける側、つまり客側であったとしてもその
都度 「ありがとう」 とか 「すみませんね」 などということばを添えるのが真の紳士
・淑女というものである。もちろん店のスタッフの対応に全く誠意がみられないとか、明ら
かに立腹させられるようなことがあれば話は別であるが、「なぜ客の側が “ありがとう”
などという必要があるのだ」 とか 「金を払っているのはこっちなんだ」 ということを
口に出さずともそういう雰囲気を感じさせるだけで、「品性のない、かわいそうな人だな
あ」 と周囲は感じてしまうものなのだ。
ファストフード店などでたとえマニュアル通りの対応をしているアルバイトのスタッフであ
っても、やはり心は十分に伝わるものである。客側の方で 「気持のよい対応をしてくれ
てありがとう」 という趣旨の一言や雰囲気を出せば、サービスを提供する側としても逆
に 「ありがとうございますという気持ちで応じたい」 となるのは普通であり、結果的に、
「より気持ちのよいサービスを受けられる恩恵に与れる」 というものではないだろうか。
以下、やはりその当人は気づいていないが、社会人としての 「常識レベル」 を知られ
てしまうような例については明日の 「こじろう117」 でこの続きとして述べることにし
たいと思う。
飼い主の何気ない一言で、時にはひどく
落ち込むことのある!? こじろう
2010年07月07日
『常識レベル』 がわかってしまう一言???(その1)
日常発する “ほんの一言” で、その人の社会人としての 「常識レベル」 が知れてしま
ったり、本性などを悟られてしまうことがある。
先日、あるデパートで 「全国銘品展」 というような催事があり、暇にまかせてノコノコと
足を延ばした時のことである。日曜日の昼頃ということもあってその特設会場は老若男女
でごった返しており、それぞれの “銘店” のコーナーでは商品を買い求めたり、精算の
ための長い行列ができたりと、どこが通路かもわからないような混雑ぶりであった。
そんななか、自分はたまたま全国的に有名なパティシエのいる洋菓子店のコーナーでケ
ーキなどが並んでいるショーケースの中を眺めていると、突然背後から 「あのう、通れな
いんですけど」 というキツイ?口調の声が耳に入った。あわてて振り返ると、ベビーカーに
乳児 (と思われる小さなこども) を乗せた若い女性が少しこちらをにらむようにして見て
いたので、「ああ、すみません」 といってすぐ道をあけた。その後もその女性はベビーカー
を押しながら大変な混雑のなか同じようなことを繰り返しながら前に進んでいったようだ
った。
たしかに一部通路をふさぐように立っていた (といっても、ごく普通の位置に立ってショ
ーケースを眺めていただけだが) 自分が、その女性 (およびベビーカー) にとって行
く手をふさぐ、つまりジャマになっていたことは事実であり、だからこそ素直に “お詫び
の一言” も添えてすぐ道をあけたわけである。しかし後でよく考えてみると、何か釈然と
しない思いが残ってしまったのである。
まず第一に 「通路をふさいでいた」 といっても、もともとそこはその時の混雑状況から
して 「通路といっても通路でないようなもの」 であることはその場にいたら誰でもわか
ることであり、そういうところでは前に進むにも 「人と人との間を縫うようにして」 いか
ざるをえない、つまり自分の望むようにまっすぐに進むのは極めて困難であると承知し、
覚悟するのが普通である。ましてそのような一人がやっとの思いで抜けていけるような
状態のなかベビーカーを押していくのは (周囲にとっても) 本当に大変なことである。
したがってそういう状況下で道をあけてほしいと思ったとしたら、それは 「あのう、通れ
ないんですけど」 という非難めいた口調でなく、「すみません、道をあけてくれませんか」
とお願いするのがふさわしいのではないだろうか。たった一言で、しかも同じ内容のこと
を意味するのにも、何かその言葉を発した人の 「社会人としての 『常識レベル』 が
知れてしまうことになる場面である」 と言ったらおおげさであろうか。
また余計なことで少し話も逸れてしまうが、そのような大変な混雑で周囲の人たちは皆
前を向いて歩いていないようななかで、ベビーカーに乳児を乗せグイグイと進んでいくの
もいかがなものであろうかと思われる。もし誰かが偶然勢いよくベビーカーにぶつかって
きたりでもしたら大変危険な事態が予想されるし、また季節的に可能性は小さいとはい
え、風邪でも移されたらどうするのかという心配もある。そのこどもにとっても、公園など
の緑の中をゆっくり散歩するのとは異なり、極めてザワザワしたなかで決して快適で楽し
い空間、時間であるとはいえないだろう。まあ、このことについてはその女性 (おそらく
母親) なりの考えがあってのことだろうから、他人がいろいろ口を出すことではないが、
いずれにしてもあまりほめられたこととはいえない気がして仕方がない。
話を元に戻すと、日常たかが一言でもそれが何気ない場面であればあるほど、その人の
本性とか人格が現れてしまうことはあると思われる。この続きは明日の 「こじろう117」
で述べることにしたい。
飼い主を無視して前にグイグイ進んで
いきたいのを必死で我慢することがよ
くある!? こじろう
ったり、本性などを悟られてしまうことがある。
先日、あるデパートで 「全国銘品展」 というような催事があり、暇にまかせてノコノコと
足を延ばした時のことである。日曜日の昼頃ということもあってその特設会場は老若男女
でごった返しており、それぞれの “銘店” のコーナーでは商品を買い求めたり、精算の
ための長い行列ができたりと、どこが通路かもわからないような混雑ぶりであった。
そんななか、自分はたまたま全国的に有名なパティシエのいる洋菓子店のコーナーでケ
ーキなどが並んでいるショーケースの中を眺めていると、突然背後から 「あのう、通れな
いんですけど」 というキツイ?口調の声が耳に入った。あわてて振り返ると、ベビーカーに
乳児 (と思われる小さなこども) を乗せた若い女性が少しこちらをにらむようにして見て
いたので、「ああ、すみません」 といってすぐ道をあけた。その後もその女性はベビーカー
を押しながら大変な混雑のなか同じようなことを繰り返しながら前に進んでいったようだ
った。
たしかに一部通路をふさぐように立っていた (といっても、ごく普通の位置に立ってショ
ーケースを眺めていただけだが) 自分が、その女性 (およびベビーカー) にとって行
く手をふさぐ、つまりジャマになっていたことは事実であり、だからこそ素直に “お詫び
の一言” も添えてすぐ道をあけたわけである。しかし後でよく考えてみると、何か釈然と
しない思いが残ってしまったのである。
まず第一に 「通路をふさいでいた」 といっても、もともとそこはその時の混雑状況から
して 「通路といっても通路でないようなもの」 であることはその場にいたら誰でもわか
ることであり、そういうところでは前に進むにも 「人と人との間を縫うようにして」 いか
ざるをえない、つまり自分の望むようにまっすぐに進むのは極めて困難であると承知し、
覚悟するのが普通である。ましてそのような一人がやっとの思いで抜けていけるような
状態のなかベビーカーを押していくのは (周囲にとっても) 本当に大変なことである。
したがってそういう状況下で道をあけてほしいと思ったとしたら、それは 「あのう、通れ
ないんですけど」 という非難めいた口調でなく、「すみません、道をあけてくれませんか」
とお願いするのがふさわしいのではないだろうか。たった一言で、しかも同じ内容のこと
を意味するのにも、何かその言葉を発した人の 「社会人としての 『常識レベル』 が
知れてしまうことになる場面である」 と言ったらおおげさであろうか。
また余計なことで少し話も逸れてしまうが、そのような大変な混雑で周囲の人たちは皆
前を向いて歩いていないようななかで、ベビーカーに乳児を乗せグイグイと進んでいくの
もいかがなものであろうかと思われる。もし誰かが偶然勢いよくベビーカーにぶつかって
きたりでもしたら大変危険な事態が予想されるし、また季節的に可能性は小さいとはい
え、風邪でも移されたらどうするのかという心配もある。そのこどもにとっても、公園など
の緑の中をゆっくり散歩するのとは異なり、極めてザワザワしたなかで決して快適で楽し
い空間、時間であるとはいえないだろう。まあ、このことについてはその女性 (おそらく
母親) なりの考えがあってのことだろうから、他人がいろいろ口を出すことではないが、
いずれにしてもあまりほめられたこととはいえない気がして仕方がない。
話を元に戻すと、日常たかが一言でもそれが何気ない場面であればあるほど、その人の
本性とか人格が現れてしまうことはあると思われる。この続きは明日の 「こじろう117」
で述べることにしたい。
飼い主を無視して前にグイグイ進んで
いきたいのを必死で我慢することがよ
くある!? こじろう
2010年07月06日
『傍観者』 でいられるか???(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・『傍観者』 でいられるか???(その1)・・・の続きである。
今回のバスにおけるような出来事があった際、後になって客観的な立場でいろいろと論ずる
のは簡単であるが、「自分がその当事者 (その場に居合わせた一乗客) として『傍観者』
になることなく、即座に適切でスマートな行動がとれるかどうか」 というのにはなんともいえ
ない難しさがあると思われる。そのためには以下のようなことをクリアしていく必要があるか
らである。
1. 100円という金額自体に抵抗を感ずる人はいないにしても、実際他のそれなりの数
の乗客が注視しているなかで、「私が立て替えます」 とか 「私が両替します」 と
言い出すのはそれなりの勇気と覚悟が必要である。というのもこういう場合、相手の
人がその善意 (申し出) を必ずしも快く受け入れてくれるとは限らないからである。
「余計なことをしてくれるな」 といわれる可能性はかなり小さいとしても、もし固辞さ
れた場合はショックであるし、いろいろ気まずい思いをすることにもなってしまう。
2. 「立て替え」 を受け入れてくれた場合でも、相手がごく普通の常識をわきまえた人で
あれば (金額の大小はともかく) それをそのままにしておくことはまずあり得ない。
たまたま降車場所が同じであれば別として、そうでない (可能性の方が高いと思わ
れるが) 場合にはその精算などなかなかややこしいことになるのは必至である。
「いや、たかが100円程度のことなので結構です」 というのは簡単であるし、で
きれば極力そうしたいところであるが、それでは相手の人のプライドを傷つけること
になり、せっかくの善意が台無しになってしまう可能性もあるのだ。それでは 「ぜ
ひ、ご住所とお名前をお教えください」 などといわれるのも 「100円程度のこ
ことでそんな」 と気が引けてしまい、そこにしばらくはまたやっかいなやり取りが
生じてしまうだろう。また何よりかなり照れくさいことでもある。
3. 「運転手の立場」 の考慮も必要である。今回の件で運転手のとった姿勢、態度に対し
「少々冷たいのではないか」 と非難するのは簡単だが、それはいかにも早計という
ものである。その運転手としてはバス会社の一員としてその方針を忠実に遵守してい
るだけかもしれないし、また 「個人的に両替できるくらいの準備をしておくのが、
運転手としてのあるべき姿である」 というのもたやすいが、それも管理の問題など
いろいろと外部にはわからぬ事情があるかもしれない。運転手としてはもしかすると
「個人的には何とかしてあげたいのは山々である。でも会社の方針に一人逆らうこと
はできないし、他の乗客にいらぬ心配や迷惑をかけるわけにもいかない」 との葛藤
に苦しんでいるかもしれないのだ。
とすれば自分が出ていくことによって、 「その運転手の顔をつぶしてしまう」 ある
いは 「運転手にバツの悪い思いをさせてしまうかもしれない」 という可能性すら
考えなくてはならないだろう。
以上のほかにも、冷静に考えたときに、ことに (両替でなく) 「立て替え」 ともなれば、
そこにはさまざまな目に見えない障壁が立ちはだかるのである。
今回投稿された82歳の男性のように、ある意味人生を達観されているような方はともかく、
「『傍観者』 にならずにとっさに適切な行動がとれるか」 あるいは 「 『君子危うきに
近寄らず』 と 『傍観者』 を決め込むか」 の適切な選択をするにも、やはりそれなりの
“人生修行・修養” といったものがどうしても必要ということになるのであろうか。
飼い犬としての “修行や修養” とは何か、
常に自問している!? こじろう
今回のバスにおけるような出来事があった際、後になって客観的な立場でいろいろと論ずる
のは簡単であるが、「自分がその当事者 (その場に居合わせた一乗客) として『傍観者』
になることなく、即座に適切でスマートな行動がとれるかどうか」 というのにはなんともいえ
ない難しさがあると思われる。そのためには以下のようなことをクリアしていく必要があるか
らである。
1. 100円という金額自体に抵抗を感ずる人はいないにしても、実際他のそれなりの数
の乗客が注視しているなかで、「私が立て替えます」 とか 「私が両替します」 と
言い出すのはそれなりの勇気と覚悟が必要である。というのもこういう場合、相手の
人がその善意 (申し出) を必ずしも快く受け入れてくれるとは限らないからである。
「余計なことをしてくれるな」 といわれる可能性はかなり小さいとしても、もし固辞さ
れた場合はショックであるし、いろいろ気まずい思いをすることにもなってしまう。
2. 「立て替え」 を受け入れてくれた場合でも、相手がごく普通の常識をわきまえた人で
あれば (金額の大小はともかく) それをそのままにしておくことはまずあり得ない。
たまたま降車場所が同じであれば別として、そうでない (可能性の方が高いと思わ
れるが) 場合にはその精算などなかなかややこしいことになるのは必至である。
「いや、たかが100円程度のことなので結構です」 というのは簡単であるし、で
きれば極力そうしたいところであるが、それでは相手の人のプライドを傷つけること
になり、せっかくの善意が台無しになってしまう可能性もあるのだ。それでは 「ぜ
ひ、ご住所とお名前をお教えください」 などといわれるのも 「100円程度のこ
ことでそんな」 と気が引けてしまい、そこにしばらくはまたやっかいなやり取りが
生じてしまうだろう。また何よりかなり照れくさいことでもある。
3. 「運転手の立場」 の考慮も必要である。今回の件で運転手のとった姿勢、態度に対し
「少々冷たいのではないか」 と非難するのは簡単だが、それはいかにも早計という
ものである。その運転手としてはバス会社の一員としてその方針を忠実に遵守してい
るだけかもしれないし、また 「個人的に両替できるくらいの準備をしておくのが、
運転手としてのあるべき姿である」 というのもたやすいが、それも管理の問題など
いろいろと外部にはわからぬ事情があるかもしれない。運転手としてはもしかすると
「個人的には何とかしてあげたいのは山々である。でも会社の方針に一人逆らうこと
はできないし、他の乗客にいらぬ心配や迷惑をかけるわけにもいかない」 との葛藤
に苦しんでいるかもしれないのだ。
とすれば自分が出ていくことによって、 「その運転手の顔をつぶしてしまう」 ある
いは 「運転手にバツの悪い思いをさせてしまうかもしれない」 という可能性すら
考えなくてはならないだろう。
以上のほかにも、冷静に考えたときに、ことに (両替でなく) 「立て替え」 ともなれば、
そこにはさまざまな目に見えない障壁が立ちはだかるのである。
今回投稿された82歳の男性のように、ある意味人生を達観されているような方はともかく、
「『傍観者』 にならずにとっさに適切な行動がとれるか」 あるいは 「 『君子危うきに
近寄らず』 と 『傍観者』 を決め込むか」 の適切な選択をするにも、やはりそれなりの
“人生修行・修養” といったものがどうしても必要ということになるのであろうか。
飼い犬としての “修行や修養” とは何か、
常に自問している!? こじろう
2010年07月05日
『傍観者』 でいられるか???(その1)
先日某紙朝刊の 「私の声」 という欄に 「運賃両替 バスでの後悔」 というタイトルで
82歳の男性の投稿が掲載されていた。
その内容は、
「駅まで100円という区間のバスの中。Z寺参りの帰りか、ショルダーバッグを掛けた実直
そうな中年男性があたふたと乗り込んできた。運転手に 『5000円札は両替できないで
すかねえ』 と聞いている。 『5000円はダメだね。降りて細かくしてきてくれない?』 と
運転手は恐縮するふうもなく答えた。 (中略) その男性は困ったような顔をして降りて
いった。動き出したバスの窓から、彼のとぼとぼ歩いている姿が目に入った。新幹線の都合
とか、予定の時刻に間に合わなかった場合を考えると、少々胸が痛んだ。 (中略) 両替機
が受け付けないからといって、わずかな運賃のことで乗客を降ろしてしまうのは少々冷たい
のではないか。乗客にとっても、せっかくのZ寺参りを後味の悪いものにしてしまったので
はないかと残念に思った。家でこの話をしたら、『どうしてあなたが立て替えてあげなかっ
たの?』 と妻のひと言。とっさに気づかなかったとはいえ、これは参った一本とられた。
傍観者を決め込んでぼーっとしていた小生が一番悪かったのかもしれないと、後悔のほぞ
をかんでいる」
というものである。
今回のこの場面における、バス運転手やバス会社の対応については道路運送法上の解
釈はともかくとして、まずは 「もっともなものだ」 という見方があるだろう。それには 「た
かが100円とはいえそれは正当な運賃として当然徴収しなくてはならないし、また普通
バスのような公共交通機関を利用する際にはあらかじめ小銭を用意しておくなどは常識で
あるともいえる。さらには運転手がこの一人の乗客に関わっていることでバスの発車時間
に遅れが出るなどとなれば、 (他人に迷惑をかけないように) しっかりと小銭を用意し
てきている他の乗客に迷惑をかけることになる」 などの理由が考えられる。
しかしまた見方を変えれば、この82歳の男性が感じているように (バス運転手および
バス会社の対応は) 「少々冷たいのではないか」 という意見も少なくないと思われる。
それは 「誰でもたまたま小銭の持ち合わせがないことはありうるし、普通はどのような
業種でも客側の支払いに対して即座に釣銭などを出せるようにしておくこともまた常識で
ある。両替機にしても高額紙幣に対応できないものしか設置してないのは、バス会社側
の事情によるものではないか。またその場で支払えなくても目的地に到着後、何らかの
方法で支払うことは可能であり、そもそもこのような理由で乗車そのものを拒否するのは
道路運送法に抵触するのではないか」 などという論拠である。
厳密な法的解釈についてここで論ずるつもりはないし、またこのような場合の対処の仕方
はバス会社によって異なっていたり、あるいはその会社の内部でさえ乗務員によりその対
応はさまざまである可能性も高い。したがって今ここで 「バス運転手、バス会社はこう
いう場合どうすべきであるか」 ということをテーマとするのはいろいろな意味で現実的
ではないが、少なくとも投稿した男性のように 「自分がその場にいたとしたら果たして
どういう立場、行動をとることができただろうか」 ということを考えるには格好の機会で
あるかもしれない。この続きは改めて 「こじろう117」 にて述べることにしたいと思う。
飼い主の自動車に自ら 「乗車拒否」 を
して困らせることのある!? こじろう
82歳の男性の投稿が掲載されていた。
その内容は、
「駅まで100円という区間のバスの中。Z寺参りの帰りか、ショルダーバッグを掛けた実直
そうな中年男性があたふたと乗り込んできた。運転手に 『5000円札は両替できないで
すかねえ』 と聞いている。 『5000円はダメだね。降りて細かくしてきてくれない?』 と
運転手は恐縮するふうもなく答えた。 (中略) その男性は困ったような顔をして降りて
いった。動き出したバスの窓から、彼のとぼとぼ歩いている姿が目に入った。新幹線の都合
とか、予定の時刻に間に合わなかった場合を考えると、少々胸が痛んだ。 (中略) 両替機
が受け付けないからといって、わずかな運賃のことで乗客を降ろしてしまうのは少々冷たい
のではないか。乗客にとっても、せっかくのZ寺参りを後味の悪いものにしてしまったので
はないかと残念に思った。家でこの話をしたら、『どうしてあなたが立て替えてあげなかっ
たの?』 と妻のひと言。とっさに気づかなかったとはいえ、これは参った一本とられた。
傍観者を決め込んでぼーっとしていた小生が一番悪かったのかもしれないと、後悔のほぞ
をかんでいる」
というものである。
今回のこの場面における、バス運転手やバス会社の対応については道路運送法上の解
釈はともかくとして、まずは 「もっともなものだ」 という見方があるだろう。それには 「た
かが100円とはいえそれは正当な運賃として当然徴収しなくてはならないし、また普通
バスのような公共交通機関を利用する際にはあらかじめ小銭を用意しておくなどは常識で
あるともいえる。さらには運転手がこの一人の乗客に関わっていることでバスの発車時間
に遅れが出るなどとなれば、 (他人に迷惑をかけないように) しっかりと小銭を用意し
てきている他の乗客に迷惑をかけることになる」 などの理由が考えられる。
しかしまた見方を変えれば、この82歳の男性が感じているように (バス運転手および
バス会社の対応は) 「少々冷たいのではないか」 という意見も少なくないと思われる。
それは 「誰でもたまたま小銭の持ち合わせがないことはありうるし、普通はどのような
業種でも客側の支払いに対して即座に釣銭などを出せるようにしておくこともまた常識で
ある。両替機にしても高額紙幣に対応できないものしか設置してないのは、バス会社側
の事情によるものではないか。またその場で支払えなくても目的地に到着後、何らかの
方法で支払うことは可能であり、そもそもこのような理由で乗車そのものを拒否するのは
道路運送法に抵触するのではないか」 などという論拠である。
厳密な法的解釈についてここで論ずるつもりはないし、またこのような場合の対処の仕方
はバス会社によって異なっていたり、あるいはその会社の内部でさえ乗務員によりその対
応はさまざまである可能性も高い。したがって今ここで 「バス運転手、バス会社はこう
いう場合どうすべきであるか」 ということをテーマとするのはいろいろな意味で現実的
ではないが、少なくとも投稿した男性のように 「自分がその場にいたとしたら果たして
どういう立場、行動をとることができただろうか」 ということを考えるには格好の機会で
あるかもしれない。この続きは改めて 「こじろう117」 にて述べることにしたいと思う。
飼い主の自動車に自ら 「乗車拒否」 を
して困らせることのある!? こじろう
2010年07月04日
ヒドすぎる 『コスト意識』!!!(最終回)
ヒドすぎる 『コスト意識』!!! (その1) (その2) (その3) に続く、このシリーズの
最終回である。
(その3) までは主として官公庁の行なう一部業務における、極めて薄弱であると思われる
「コスト意識」 について述べてきたが、今日はさらに今回のようなテーマに潜む “根本的”
な問題部分について触れてみたいと思う。
今回この問題を考える発端となったのは、経産省某庁がアンケート回収業務を委託した業者
の女性スタッフからの電話であるが、今振り返れば、それはなかなか強硬な “ものいい”
から始まっていた。しかし、当方から (思いがけず?) 反論されるうちに、次第にトーンが
変わり、最終的には 「何とかお願いします」 という懇願スタイルになってきたのである。
「最初はとりあえず “強く” 出る。それが通用しないとわかると途端に “下手に” 出る」
とは、なにか 「どこかの世界」 に通ずるものがあるような気もするが、それはともかくとし
てこの手の業務、経産省の職員が直接携わろうと (その可能性は限りなく小さいだろうが)
委託先企業等のスタッフが行なおうと、実は最初から 「お願いスタイル」 で臨むのが筋な
のである。
というのも今回のアンケートに関する業務、彼らにとっては当然 “本業” として行なってい
る、つまり彼らはこのことで正規の報酬 (給与) を得ているのに対し、アンケートに答え
る事業所、一般国民の側は自らの本来業務とは何ら関係のないこと、すなわちハッキリ
いえば 「時間と労力と場合によってはそれなりの自己経費負担」 までかけて全く自らの
利益に直接結びつかないことを 「協力して “あげて” いる」 のである。強制力を有した
国家権力による行政上の処分や指導が行われる場合とは根本的に異なるのだ。
したがって 「国家機関による調査なのだからツベコベいわず、素直に応じて当然である」
というような尊大な考え方は改め、「国家施策遂行のために、ここはひとつ何とかご協力
いただけないでしょうか」 という姿勢を示すべきなのである。もっとも書面上はそういった
趣旨を某庁長官名で述べているが、これも官公署業務の常で、実態が伴っているとは到
底思えない代物になっているのである。
今回は一連のことを通じて官公庁の一部業務について批判する立場をとってきたが、そ
のなかにはわれわれ民間側、一般国民側にも大いに反面教師とすべき点が含まれてい
ると考えなくてはならない。それはたとえば 「自分にとっての本業、あるいは利益を生む
ものが、相手方にとっては必ずしもそうではない、もしくは不利益にさえなりうる可能性を
含んでいるということを常に念頭においておくことが肝要である」 などであろうか。
飼い主が自分に芸を仕込む際、それを
「当然のこと」 と思わず、「おぼえて
いただきたい」 というスタイルにすべ
きであると考えている!? こじろう
最終回である。
(その3) までは主として官公庁の行なう一部業務における、極めて薄弱であると思われる
「コスト意識」 について述べてきたが、今日はさらに今回のようなテーマに潜む “根本的”
な問題部分について触れてみたいと思う。
今回この問題を考える発端となったのは、経産省某庁がアンケート回収業務を委託した業者
の女性スタッフからの電話であるが、今振り返れば、それはなかなか強硬な “ものいい”
から始まっていた。しかし、当方から (思いがけず?) 反論されるうちに、次第にトーンが
変わり、最終的には 「何とかお願いします」 という懇願スタイルになってきたのである。
「最初はとりあえず “強く” 出る。それが通用しないとわかると途端に “下手に” 出る」
とは、なにか 「どこかの世界」 に通ずるものがあるような気もするが、それはともかくとし
てこの手の業務、経産省の職員が直接携わろうと (その可能性は限りなく小さいだろうが)
委託先企業等のスタッフが行なおうと、実は最初から 「お願いスタイル」 で臨むのが筋な
のである。
というのも今回のアンケートに関する業務、彼らにとっては当然 “本業” として行なってい
る、つまり彼らはこのことで正規の報酬 (給与) を得ているのに対し、アンケートに答え
る事業所、一般国民の側は自らの本来業務とは何ら関係のないこと、すなわちハッキリ
いえば 「時間と労力と場合によってはそれなりの自己経費負担」 までかけて全く自らの
利益に直接結びつかないことを 「協力して “あげて” いる」 のである。強制力を有した
国家権力による行政上の処分や指導が行われる場合とは根本的に異なるのだ。
したがって 「国家機関による調査なのだからツベコベいわず、素直に応じて当然である」
というような尊大な考え方は改め、「国家施策遂行のために、ここはひとつ何とかご協力
いただけないでしょうか」 という姿勢を示すべきなのである。もっとも書面上はそういった
趣旨を某庁長官名で述べているが、これも官公署業務の常で、実態が伴っているとは到
底思えない代物になっているのである。
今回は一連のことを通じて官公庁の一部業務について批判する立場をとってきたが、そ
のなかにはわれわれ民間側、一般国民側にも大いに反面教師とすべき点が含まれてい
ると考えなくてはならない。それはたとえば 「自分にとっての本業、あるいは利益を生む
ものが、相手方にとっては必ずしもそうではない、もしくは不利益にさえなりうる可能性を
含んでいるということを常に念頭においておくことが肝要である」 などであろうか。
飼い主が自分に芸を仕込む際、それを
「当然のこと」 と思わず、「おぼえて
いただきたい」 というスタイルにすべ
きであると考えている!? こじろう
2010年07月03日
ヒドすぎる 『コスト意識』!!!(その3)
「こじろう117」・・・ヒドすぎる 『コスト意識』!!! (その1) および (その2) の続き
である。
(その2) の最後に書いた、今回の件についてある筋から確認した当局 (経産省所管の
某庁幹部) による 「驚くべき見解」 は以下のようなものである。
質問1. なぜ電話で一言伝えれば済ませられるはずのこと (今回でいえば 「アンケート
に回答しない旨」) をわざわざ余計なコストをかけ書類を再送してまで行なわなけれ
ばならないのか。
<当局の見解>
当局では “業務委託先” に対してそのような指示は出していない。(書類再送が
ムダな過程だと認めたうえで) 委託先が (勝手に) 判断して行なっていることで
ある。
この言い分、一体どういう顔をして言えるのだろうか。「経産省某庁長官名」 で出されてい
るアンケートである。実際に関係業務を行なっているのが経産省の職員であろうと、委託先
のスタッフであろうと、それは国民の知ったことではない。この件に関する最終責任は経済
産業大臣ならびに所管の某庁長官が負うものであるのは小学生でもわかるような基本的な
ことである。また、そういうことなら経費 (国民の血税) も “使い放題” ということになる
だろう。(後で一つ一つチェックするとも言っているらしいが、それも “形骸化されたもの” な
のは明らかである)
たとえば民間のメーカーが製造・販売した製品に欠陥のあることが明らかになった場合、た
とえその原因がメーカーの下請け、孫請け業者の工程にあったとしても、まさか 「当方の
ミスではありません。下請け、関連会社のミスです」 というようなことが世間で通用するで
あろうか。それどころかそのようなことをほんの少しでもほのめかした瞬間、そのメーカーの
生命は絶たれるというくらいの一大事である。監督官庁のいうこととは到底思えない、無
責任極まりない言い分である。
質問2. 「回答しない」 のに、なぜそのことをいちいち書類として残すというような意味の
ないことをするのか。
<当局の見解>
書類として形にしておかないと、委託先のスタッフが本当に事業所と連絡をとっ
たかどうかの確認ができない。確認をとったということが架空の話では困る。
これもまったくもって理解に苦しむ見解である。 そもそも国の政策遂行上大事な?アンケ
ート回収業務をなぜそのような 「信頼のおけない」 業者に委託するのかという疑問が先
に生じてしまう。また経産省と業務委託先との間の信頼関係や委託先企業内部のスタッフ
に対する信用問題まで、なぜ国民がその血税をもってして担保しなくてはならないのか。
どのような組織、企業であろうとも、そのスタッフは当然誠実に業務に携わることが前提
であり、それができないものは最初から排除されるべきである。もしかしたら 「不祥事の
温床・巣窟」 と呼ばれた “旧社会保険庁” の二の舞となることをあらかじめ防ごうと
しているのかもしれないが、それにしてもそんな根本的な個人的モラルに関することまで
国民に負担させようとしているとは言語道断といえよう。
以下、単なるコスト意識の欠如にとどまらない、官公署のこの手の業務についての根本
的問題については、まとめとして明日の 「こじろう117」 で続きを述べることにしたい
と思う。
自分に対するしつけに関して、飼い主側の
「驚くべき言い分」 に納得のいかない点
がたくさんある!? こじろう
である。
(その2) の最後に書いた、今回の件についてある筋から確認した当局 (経産省所管の
某庁幹部) による 「驚くべき見解」 は以下のようなものである。
質問1. なぜ電話で一言伝えれば済ませられるはずのこと (今回でいえば 「アンケート
に回答しない旨」) をわざわざ余計なコストをかけ書類を再送してまで行なわなけれ
ばならないのか。
<当局の見解>
当局では “業務委託先” に対してそのような指示は出していない。(書類再送が
ムダな過程だと認めたうえで) 委託先が (勝手に) 判断して行なっていることで
ある。
この言い分、一体どういう顔をして言えるのだろうか。「経産省某庁長官名」 で出されてい
るアンケートである。実際に関係業務を行なっているのが経産省の職員であろうと、委託先
のスタッフであろうと、それは国民の知ったことではない。この件に関する最終責任は経済
産業大臣ならびに所管の某庁長官が負うものであるのは小学生でもわかるような基本的な
ことである。また、そういうことなら経費 (国民の血税) も “使い放題” ということになる
だろう。(後で一つ一つチェックするとも言っているらしいが、それも “形骸化されたもの” な
のは明らかである)
たとえば民間のメーカーが製造・販売した製品に欠陥のあることが明らかになった場合、た
とえその原因がメーカーの下請け、孫請け業者の工程にあったとしても、まさか 「当方の
ミスではありません。下請け、関連会社のミスです」 というようなことが世間で通用するで
あろうか。それどころかそのようなことをほんの少しでもほのめかした瞬間、そのメーカーの
生命は絶たれるというくらいの一大事である。監督官庁のいうこととは到底思えない、無
責任極まりない言い分である。
質問2. 「回答しない」 のに、なぜそのことをいちいち書類として残すというような意味の
ないことをするのか。
<当局の見解>
書類として形にしておかないと、委託先のスタッフが本当に事業所と連絡をとっ
たかどうかの確認ができない。確認をとったということが架空の話では困る。
これもまったくもって理解に苦しむ見解である。 そもそも国の政策遂行上大事な?アンケ
ート回収業務をなぜそのような 「信頼のおけない」 業者に委託するのかという疑問が先
に生じてしまう。また経産省と業務委託先との間の信頼関係や委託先企業内部のスタッフ
に対する信用問題まで、なぜ国民がその血税をもってして担保しなくてはならないのか。
どのような組織、企業であろうとも、そのスタッフは当然誠実に業務に携わることが前提
であり、それができないものは最初から排除されるべきである。もしかしたら 「不祥事の
温床・巣窟」 と呼ばれた “旧社会保険庁” の二の舞となることをあらかじめ防ごうと
しているのかもしれないが、それにしてもそんな根本的な個人的モラルに関することまで
国民に負担させようとしているとは言語道断といえよう。
以下、単なるコスト意識の欠如にとどまらない、官公署のこの手の業務についての根本
的問題については、まとめとして明日の 「こじろう117」 で続きを述べることにしたい
と思う。
自分に対するしつけに関して、飼い主側の
「驚くべき言い分」 に納得のいかない点
がたくさんある!? こじろう
2010年07月02日
ヒドすぎる 『コスト意識』!!!(その2)
昨日の 「こじろう117」・・・ヒドすぎる 『コスト意識』!!!(その1)・・・の続きである。
経産省所管の某庁から “任意の協力” という名目で届いた 「△△統計の調査」 アンケ
ート (「こじろう117」・・・「明らかな 『ムダ』 は許されない」 参照) 。あまりにも手間
のかかりそうなものなのでそのまま回答せずにいたところ、当局関係 (委託先) から
「回答しないのなら改めて 『回答しない旨』 を書面で提出するように」 と電話が入った
件、ならびにそれに関わる “余計な” 諸経費について 「当局側に 『コスト意識』 とい
うものがたとえわずかでも存在するのかという疑念」 についてが昨日の内容である。
官公署というのは民間ではできない業務を遂行するのが本来であるため、そこには基本
的に 「利益を生み出す」 という概念のないのは当然である。またそれゆえに、その事業
には民間の一企業などでは到底投入できないような膨大な費用をかける必要があるものも
当然存在する。「行政」 とはそういうもので、そもそも民間と同レベル、同じ目線で比較す
ることにはしょせん無理があるのは否定できない。
しかし、だからといってそれではなんでもかんでも無制限に行なったり、費用も無制限に
かけていいということには決してならず、むしろ国民の血税がその原資になっている以上、
“より厳しい視線が注がれなくてはならないもの” ともいえるだろう。
個人的には今回のこのアンケート調査、これだけの費用 (具体的なことはわからないが
立案の段階から最終的な集計、資料の作成まで一切合切でいえば、どう少なく見積もって
も数千万円単位にはなるだろう) をかけ、さらに抽出された事業所に非常に大きな負担
を強いてまで実施する価値があるのだろうかという疑念は相変わらず払拭できないが、そ
の点については、逆に価値がないとも言い切れる根拠は何ももちあわせていない “ど素人”
として、これ以上いろいろ言うのは差し控えたいと思う。
しかし、今回のように 「回答しない旨を伝える」 という統計調査アンケートの趣旨とは
まったく関係のないことにまで 「形式的な書類のやり取り」 をすることの無意味さは、
いくら “ど素人” でも感ずることができるものである。
正式な形で書面を残しておくのは、官公署、民間を問わず極めて数多いさまざまな場面
で必要とされることであるが、今回のように 「あくまでも任意の協力」 のもとに行なわれ
るものについて、なぜ書類を再送するコストをかけて、しかも 「回答しない旨を伝える」
程度のものを正式に残しておく必要があるのだろうか。
実はある筋を介して確認したところの、この件についての当局 (経産省所管の某庁幹部)
による 「驚きの見解」 については、明日の 「こじろう117」 で詳しく紹介することに
したいと思う。
飼い主から見て、「なぜこんなことを
一生懸命しているんだろう」 という
ことが極めて多い!? こじろう
経産省所管の某庁から “任意の協力” という名目で届いた 「△△統計の調査」 アンケ
ート (「こじろう117」・・・「明らかな 『ムダ』 は許されない」 参照) 。あまりにも手間
のかかりそうなものなのでそのまま回答せずにいたところ、当局関係 (委託先) から
「回答しないのなら改めて 『回答しない旨』 を書面で提出するように」 と電話が入った
件、ならびにそれに関わる “余計な” 諸経費について 「当局側に 『コスト意識』 とい
うものがたとえわずかでも存在するのかという疑念」 についてが昨日の内容である。
官公署というのは民間ではできない業務を遂行するのが本来であるため、そこには基本
的に 「利益を生み出す」 という概念のないのは当然である。またそれゆえに、その事業
には民間の一企業などでは到底投入できないような膨大な費用をかける必要があるものも
当然存在する。「行政」 とはそういうもので、そもそも民間と同レベル、同じ目線で比較す
ることにはしょせん無理があるのは否定できない。
しかし、だからといってそれではなんでもかんでも無制限に行なったり、費用も無制限に
かけていいということには決してならず、むしろ国民の血税がその原資になっている以上、
“より厳しい視線が注がれなくてはならないもの” ともいえるだろう。
個人的には今回のこのアンケート調査、これだけの費用 (具体的なことはわからないが
立案の段階から最終的な集計、資料の作成まで一切合切でいえば、どう少なく見積もって
も数千万円単位にはなるだろう) をかけ、さらに抽出された事業所に非常に大きな負担
を強いてまで実施する価値があるのだろうかという疑念は相変わらず払拭できないが、そ
の点については、逆に価値がないとも言い切れる根拠は何ももちあわせていない “ど素人”
として、これ以上いろいろ言うのは差し控えたいと思う。
しかし、今回のように 「回答しない旨を伝える」 という統計調査アンケートの趣旨とは
まったく関係のないことにまで 「形式的な書類のやり取り」 をすることの無意味さは、
いくら “ど素人” でも感ずることができるものである。
正式な形で書面を残しておくのは、官公署、民間を問わず極めて数多いさまざまな場面
で必要とされることであるが、今回のように 「あくまでも任意の協力」 のもとに行なわれ
るものについて、なぜ書類を再送するコストをかけて、しかも 「回答しない旨を伝える」
程度のものを正式に残しておく必要があるのだろうか。
実はある筋を介して確認したところの、この件についての当局 (経産省所管の某庁幹部)
による 「驚きの見解」 については、明日の 「こじろう117」 で詳しく紹介することに
したいと思う。
飼い主から見て、「なぜこんなことを
一生懸命しているんだろう」 という
ことが極めて多い!? こじろう