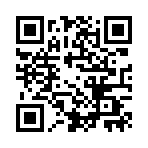2020年06月22日
恐ろしい “疑惑慣れ”???
「慣れる」 ことでプラスになるケースは多いが、それがマイナスに
働くと本当に厄介・・・なのは言うまでもない。
さて昨日の某紙 「多すぎて慣れた? アホ政権への “疑惑慣れ”
『実際にメディアや国民に起きている』 と専門家」 というタイトルの
記事の内容は、
・・・・・・アホ (アベ) 死ンゾー政権による “身内” への利益誘導は、
森友・加計問題、大学入学共通テストで予定されていた英語の
民間試験導入、桜を見る会などでも指摘されてきた。我々はそ
うした疑惑に慣らされてきている。
広島大学認知行動科学研究室の有賀敦紀准教授は言う。
「心理学の用語で 『慣れ』 は馴化と言います。人間は新しい
ものには敏感に反応しますが、徐々に時間がたつと反応しなく
なります。アホ政権の疑惑に対する慣れは実際にメディアや国
民に起きていると感じます。報道があってもなくても、疑惑が続
いていることに慣れてしまっているようです。その結果起きるこ
とはとてもシンプルで、政治に対する興味を失うだけです」
加計学園の獣医学部新設をめぐって政府を批判する元文部科
学事務次官の前川喜平氏はこう振り返る。
「私が約40年前に役所に入ったときは官僚主導でした。利益誘
導や腐敗、汚職というのも、それぞれの役所ごとに官僚が起こ
します。政治家と官僚の癒着もそれぞれ役所ごとに縦割りにあ
りました」
それが、後の政治改革で政治主導という方向にシフトする。第2
次アホ政権以降は官僚人事も掌握して官邸主導はさらに進み、
「アホ1強」 と言われる状態が続くことになった。
「政治主導は正しいと思いますが、アホ政権は政治主導というよ
りは 『官邸1強独裁体制』 と言えます。権力が集中すると利益
誘導や腐敗も自然と権力中枢に集中します。現政権の特徴はそ
こに 『改革』 という名目をつけていることです。昔は裏でこそこ
そやっていたものを、正面玄関から大きな顔をして改革を偽装し
てやるようになっています」 (前川氏)
前川氏はこうした利益誘導疑惑が続く原因の一端に 「アホ1強」
以外にもメディアの弱体化があるとみている。国会開会中は野党
の追及を報じることでメディアもそれに乗って追及しているかのよ
うにも見えるが、閉会すれば自らの調査と追及が不可欠だ。それ
が、不十分だとの認識だという。
一方で慶應義塾大学法学部の大石裕教授は違う見方をする。
「慣れ」 とは違う、メディアそのものが抱える問題だ。
「マスメディアがなぜ世論を動かすことができなくなっているかを
考えるべきです」
新聞をはじめとする既存のメディアがこの7年以上にわたるアホ
政権の疑惑を報じなかったわけではない、と大石教授は考える。
「もちろん調査報道やキャンペーン的な報道が不足していたなど
問題は個別にはあるかもしれません。しかし、過去の政権批判
と同様に報道は行われてきました。それでも一時的に支持率が
下がるだけで、その後は回復、選挙になれば自民党が勝ち続け
るという繰り返しでした」
大石教授はメディアによる権力批判が国民に響かない理由とし
て、既存のメディアへの不信があるとみる。
「大手メディアはそれぞれの立場で報じながら、一方で中立や公
平も掲げる。その矛盾に読者は気づいている。社会の中の装置
として素直に受け入れられるメディアでなくなっている」
それでも大石教授には一つの糸口のように感じることがあった。
東京高検の黒川弘務・前検事長の去就が注目された検察官の
定年延長問題だ。
「ソーシャルメディアとマスメディアがある意味で一体化し、世論
を盛り上げることで力を発揮しました」
最後は朝日新聞と産経新聞の記者らとの賭けマージャンが発覚
して黒川氏は辞任したが、ツイッターと既存メディアが重なり合っ
て世論に問いかけていき、政権の方針さえも変えるほどの影響
力を見せつけられた。
腐敗疑惑にメディアが慣れてはいけないのはもちろんだが、メデ
ィアはそれと同時に、読者にニュースが響かないことにも慣れて
はいけないということなのだ。
前出の有賀准教授はコロナ禍をきっかけにした変化も感じてい
るという。
「自分の生活に政治が直結してくるので、普段は無関心な若者
たちも政治家の発言などに敏感に反応している様子があります。
このような状況を 『脱馴化』 といいます。慣れから解放されて
新しいフェーズが始まっているようです」
持続化給付金についてはさらに疑惑が深まっている。給付金を
担当していた経産省中小企業庁の前田泰宏長官が米国視察旅
行の際に開いたパーティーで、協議会理事を務める電通関係者
と同席していたことも週刊文春の報道で発覚し、国会で追及が
始まった。元中小企業庁長官でアホ死ンゾー側近の長谷川栄
一首相補佐官がかつて顧問だったイベント会社も今回、一部を
電通子会社から請け負っていた。
利益誘導は本来、疑われることすら避けるべきだ。説明責任を
伴う権力側に 「推定無罪」 を適用させてはいけない・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というものである。
「史上最狂・史上最凶・史上最恐」 にして、やることなすことすべてが
「インチキ・イカサマ・ゴマカシ・モミケシ・マヤカシ・ゴリオシ」 である
「汚物ボクちゃん ( 『アホ』 の “A” 『バカ』 の “B” 『エ
ゴ』 の “E” = “ABE” ) 政権」 だけに、新たに不祥事やスキ
ャンダルが噴出してもさして驚かない、どころか 「ああ、またいつもの
ことね」 とばかり何も感じなくなってしまっている国民が大多数・・・な
のが本当に恐ろしく嘆かわしいが、とはいえ 「ゴキブリ以下・イエバ
エ未満・ダニ同然」 の 「汚物」 を責めてもある意味、仕方ない。
結局そんな 「クレイジー・アホ・モンスター」 を担ぎ上げて持ち上げ、
支持している (つもりの) 真の 「おバカ」 集団をなんとかしなけれ
ば、どうしようもない。
「慣れること」 のメリット・デメリットを理解
しているつもりの!? こじろう
働くと本当に厄介・・・なのは言うまでもない。
さて昨日の某紙 「多すぎて慣れた? アホ政権への “疑惑慣れ”
『実際にメディアや国民に起きている』 と専門家」 というタイトルの
記事の内容は、
・・・・・・アホ (アベ) 死ンゾー政権による “身内” への利益誘導は、
森友・加計問題、大学入学共通テストで予定されていた英語の
民間試験導入、桜を見る会などでも指摘されてきた。我々はそ
うした疑惑に慣らされてきている。
広島大学認知行動科学研究室の有賀敦紀准教授は言う。
「心理学の用語で 『慣れ』 は馴化と言います。人間は新しい
ものには敏感に反応しますが、徐々に時間がたつと反応しなく
なります。アホ政権の疑惑に対する慣れは実際にメディアや国
民に起きていると感じます。報道があってもなくても、疑惑が続
いていることに慣れてしまっているようです。その結果起きるこ
とはとてもシンプルで、政治に対する興味を失うだけです」
加計学園の獣医学部新設をめぐって政府を批判する元文部科
学事務次官の前川喜平氏はこう振り返る。
「私が約40年前に役所に入ったときは官僚主導でした。利益誘
導や腐敗、汚職というのも、それぞれの役所ごとに官僚が起こ
します。政治家と官僚の癒着もそれぞれ役所ごとに縦割りにあ
りました」
それが、後の政治改革で政治主導という方向にシフトする。第2
次アホ政権以降は官僚人事も掌握して官邸主導はさらに進み、
「アホ1強」 と言われる状態が続くことになった。
「政治主導は正しいと思いますが、アホ政権は政治主導というよ
りは 『官邸1強独裁体制』 と言えます。権力が集中すると利益
誘導や腐敗も自然と権力中枢に集中します。現政権の特徴はそ
こに 『改革』 という名目をつけていることです。昔は裏でこそこ
そやっていたものを、正面玄関から大きな顔をして改革を偽装し
てやるようになっています」 (前川氏)
前川氏はこうした利益誘導疑惑が続く原因の一端に 「アホ1強」
以外にもメディアの弱体化があるとみている。国会開会中は野党
の追及を報じることでメディアもそれに乗って追及しているかのよ
うにも見えるが、閉会すれば自らの調査と追及が不可欠だ。それ
が、不十分だとの認識だという。
一方で慶應義塾大学法学部の大石裕教授は違う見方をする。
「慣れ」 とは違う、メディアそのものが抱える問題だ。
「マスメディアがなぜ世論を動かすことができなくなっているかを
考えるべきです」
新聞をはじめとする既存のメディアがこの7年以上にわたるアホ
政権の疑惑を報じなかったわけではない、と大石教授は考える。
「もちろん調査報道やキャンペーン的な報道が不足していたなど
問題は個別にはあるかもしれません。しかし、過去の政権批判
と同様に報道は行われてきました。それでも一時的に支持率が
下がるだけで、その後は回復、選挙になれば自民党が勝ち続け
るという繰り返しでした」
大石教授はメディアによる権力批判が国民に響かない理由とし
て、既存のメディアへの不信があるとみる。
「大手メディアはそれぞれの立場で報じながら、一方で中立や公
平も掲げる。その矛盾に読者は気づいている。社会の中の装置
として素直に受け入れられるメディアでなくなっている」
それでも大石教授には一つの糸口のように感じることがあった。
東京高検の黒川弘務・前検事長の去就が注目された検察官の
定年延長問題だ。
「ソーシャルメディアとマスメディアがある意味で一体化し、世論
を盛り上げることで力を発揮しました」
最後は朝日新聞と産経新聞の記者らとの賭けマージャンが発覚
して黒川氏は辞任したが、ツイッターと既存メディアが重なり合っ
て世論に問いかけていき、政権の方針さえも変えるほどの影響
力を見せつけられた。
腐敗疑惑にメディアが慣れてはいけないのはもちろんだが、メデ
ィアはそれと同時に、読者にニュースが響かないことにも慣れて
はいけないということなのだ。
前出の有賀准教授はコロナ禍をきっかけにした変化も感じてい
るという。
「自分の生活に政治が直結してくるので、普段は無関心な若者
たちも政治家の発言などに敏感に反応している様子があります。
このような状況を 『脱馴化』 といいます。慣れから解放されて
新しいフェーズが始まっているようです」
持続化給付金についてはさらに疑惑が深まっている。給付金を
担当していた経産省中小企業庁の前田泰宏長官が米国視察旅
行の際に開いたパーティーで、協議会理事を務める電通関係者
と同席していたことも週刊文春の報道で発覚し、国会で追及が
始まった。元中小企業庁長官でアホ死ンゾー側近の長谷川栄
一首相補佐官がかつて顧問だったイベント会社も今回、一部を
電通子会社から請け負っていた。
利益誘導は本来、疑われることすら避けるべきだ。説明責任を
伴う権力側に 「推定無罪」 を適用させてはいけない・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というものである。
「史上最狂・史上最凶・史上最恐」 にして、やることなすことすべてが
「インチキ・イカサマ・ゴマカシ・モミケシ・マヤカシ・ゴリオシ」 である
「汚物ボクちゃん ( 『アホ』 の “A” 『バカ』 の “B” 『エ
ゴ』 の “E” = “ABE” ) 政権」 だけに、新たに不祥事やスキ
ャンダルが噴出してもさして驚かない、どころか 「ああ、またいつもの
ことね」 とばかり何も感じなくなってしまっている国民が大多数・・・な
のが本当に恐ろしく嘆かわしいが、とはいえ 「ゴキブリ以下・イエバ
エ未満・ダニ同然」 の 「汚物」 を責めてもある意味、仕方ない。
結局そんな 「クレイジー・アホ・モンスター」 を担ぎ上げて持ち上げ、
支持している (つもりの) 真の 「おバカ」 集団をなんとかしなけれ
ば、どうしようもない。
「慣れること」 のメリット・デメリットを理解
しているつもりの!? こじろう