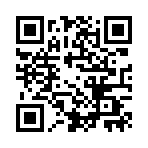2009年12月12日
「親の責任は重大」
つい先日、今年つけられた新生児の名前ランキングを発表している
テレビ番組を観る機会があった。このようなランキングは以前からあ
ったと思うが、確かにその時代の世相などを反映している部分も大
きく興味深い。
人の名前というのはその人だけの「固有の財産」であり、ほとんどの
場合は一生つき合う(つき合わざるをえない)ものでもある。だから
たいていの親はわが子の幸福を願い、さまざまな思いをこめて、最大
限の知恵をしぼって”命名”するのが全世界共通のことであると思う。
昨今、「この名前は何と読むのだろう?」という思いをすることがしばし
ばある。中にはどうみても名づけた親しか読めそうもないものや、何か
に”こじつけた”としか思えないものも散見される。それだけ「工夫し」
「思い入れが強く」「わが子は特別」ということでつけたといえば、その
とおりかもしれない。しかし、名前というのは他人に呼んで(読んで)も
らって初めて「価値があるもの」ということもいえる。
幼少期はひらがな表記ですむだろうが、成長するに従って漢字表記に
なったときにその読み方をその都度説明しなくてはならないのは子ども
自身である。また読み方の問題だけならまだしも、あまり「変わった名
前」はやはり幼少期は「かわいい名前」ですんだとして、その後はそれ
が「いじめられる原因」になることもあり、また大人になって「恥ずかしい
思い」につながることもあるかもしれない。
親としてわが子の”命名”という「一大イベント」で自らの”好み”や”趣
味”を反映させたり、”凝る”ことも基本的には自由である。しかしそこに
は、そうしてつけられた名前を一生背負うことになる子どもの将来に対
する「重大な責任」も当然生じてくるのである。
子どもの名前によって名づけた親自身の”教養”や”社会性”の程度が
推し量られるのも確かなことである。数百年前に兼好法師が”現代の
子どもの命名に関する問題”に既に「警鐘」を鳴らしていたとしか思えな
い「徒然草第116段」を、これからわが子に命名する親はしっかり読み、
その深い意味をよく考えるよう、忠告したいものである。
自分につけられた名前の”意味”が何なのか
よりも、今日のおやつは何なのかの方にに関
心がある!? こじろう
テレビ番組を観る機会があった。このようなランキングは以前からあ
ったと思うが、確かにその時代の世相などを反映している部分も大
きく興味深い。
人の名前というのはその人だけの「固有の財産」であり、ほとんどの
場合は一生つき合う(つき合わざるをえない)ものでもある。だから
たいていの親はわが子の幸福を願い、さまざまな思いをこめて、最大
限の知恵をしぼって”命名”するのが全世界共通のことであると思う。
昨今、「この名前は何と読むのだろう?」という思いをすることがしばし
ばある。中にはどうみても名づけた親しか読めそうもないものや、何か
に”こじつけた”としか思えないものも散見される。それだけ「工夫し」
「思い入れが強く」「わが子は特別」ということでつけたといえば、その
とおりかもしれない。しかし、名前というのは他人に呼んで(読んで)も
らって初めて「価値があるもの」ということもいえる。
幼少期はひらがな表記ですむだろうが、成長するに従って漢字表記に
なったときにその読み方をその都度説明しなくてはならないのは子ども
自身である。また読み方の問題だけならまだしも、あまり「変わった名
前」はやはり幼少期は「かわいい名前」ですんだとして、その後はそれ
が「いじめられる原因」になることもあり、また大人になって「恥ずかしい
思い」につながることもあるかもしれない。
親としてわが子の”命名”という「一大イベント」で自らの”好み”や”趣
味”を反映させたり、”凝る”ことも基本的には自由である。しかしそこに
は、そうしてつけられた名前を一生背負うことになる子どもの将来に対
する「重大な責任」も当然生じてくるのである。
子どもの名前によって名づけた親自身の”教養”や”社会性”の程度が
推し量られるのも確かなことである。数百年前に兼好法師が”現代の
子どもの命名に関する問題”に既に「警鐘」を鳴らしていたとしか思えな
い「徒然草第116段」を、これからわが子に命名する親はしっかり読み、
その深い意味をよく考えるよう、忠告したいものである。
自分につけられた名前の”意味”が何なのか
よりも、今日のおやつは何なのかの方にに関
心がある!? こじろう